子どものお年玉やお祝い、普通預金だと10年後いくらになる?
子どものお年玉や出産祝い、七五三祝いなど、どう管理してます?
自分である程度お金を使えるようになればいいですけど、小学校低学年くらいまでは親が管理するケースが多いでしょうか。そして、
「子ども名義の普通預金に入れて、大きくなったら渡す」
これ、多くの親がやってる王道パターンだと思います。いかがでしょう?
今回は、この王道の流れに一石を投じていきます。
この記事でわかること
- なぜ子どものお年玉を「普通預金」に入れるのか?
:親の安心感を生む心理メカニズムを行動経済学で読み解く。 - インフレがもたらす“見えない目減り”の正体
:10年後に1.8万円が消える構造と「安心料」の関係。 - 親の“損失回避”がブーストされる理由
:「子どものお金」になると、なぜ人は動けなくなるのか。 - お金を“神聖視”してしまうメンタルアカウンティング
:同じ10万円でも「使えないお金」になる心理の罠。 - 明日からできる、現実的な3つの対策
:インフレ補填、使い道の分割、子どもと一緒に考える習慣。
インフレで消えた約1.8万円の正体|親の安心料という不都合な真実
冒頭の普通預金で問題になるのが、昨今のインフレ事情です。
ここ最近の物価上昇、正直家計にガツンときますよね。これが貯金に対しても無視できない影響を与えます。ここでは便宜上インフレ率を2%、元本を10万円と仮定して計算してみましょう。(実際のインフレ率は経済状況により変動します)。また預金利息はほとんど無視できる値なので割愛します。
- 元本:10万円
- 10年後の実質価値:約8.2万円
※実質価値 = 額面 ÷ (1 + インフレ率)^年数 例:100,000 ÷ 1.02^10 ≒ 82,000(約8.2万円)
| 想定インフレ率 | 10年後の実質価値(元本10万円) |
|---|---|
| 1% | 約90,500円 |
| 2% | 約82,000円 |
| 3% | 約74,000円 |
約1.8万円が消えてる。で、この消えた1.8万円の正体、知ってます?
この1.8万円、別の見方をすると「親の心の安心料」なんです。
親が得るものは
- 「減らしてない」という安心感
- 「ちゃんと管理してる」という自己肯定感
- 「何もしなくていい」という楽さ
その対価:1.8万円(10年分)
支払者:子ども
つまり構造的にはこう:
親「子どものお金は大切に預金!」
↓
10年経過
↓
実質1.8万円目減り
↓
親「でも減ってないから良い親」
↓
そのコスト、子どもが払ってる
これ、おかしくないですか?もちろん、親が子どものお金を大切に思うからこその行動。
でも、その『大切にする』方法が、結果的に価値を目減りさせているというパラドックスが発生しています。
なぜ親は子どものお年玉を普通預金に入れっぱなしにするのか?
メンタルアカウンティングとは?子どものお金を特別視する心理
行動経済学でいうメンタルアカウンティング(心の会計)。同じお金なのに、心の中で「色分け」する現象です。
- 自分の貯金10万円 → 「自己投資に使おう」
- ボーナス10万円 → 「パーッと使おう」
- 子どものお年玉10万円 → 「絶対不可侵領域」
この最後の「絶対不可侵領域」が問題。神聖視しすぎて、結果的に目減りさせてる。
損失回避がブーストされる|子どものお金で親が動けない理由
さらに、子どものお金になると損失回避が異常に強くなる。一般に損失は利得の約2倍の精神的インパクトがあると言われています。つまり
通常:損失の痛み = 利益の喜び × 2
しかしながら、これが子どものお金となると、更に以下となりませんか?
子どもの金:損失の痛み = 利益の喜び × 2 × 親の罪悪感
この親の罪悪感ブーストで絶対減らせない病が発生します。
【会話で学ぶ】インフレ2%の影響を計算してみた結果
お年玉を預金した日

子どものお年玉と頂いたお祝いの10万円、ちゃんと子ども名義の口座作って預けたで!

偉いな。で、インフレ対策はなんか考えてるんか?

インフレ対策?なにそれ?預金なら減らへんやん?

物価、毎年2%くらい上がってるやん。額面は減らへんよ?でも価値は減る。10年後、その10万円で買えるもの8.2万円分やで。ほんでその差額1.8万円、なんの代金かわかる?

…何?

「きつい言い方するで?何もしなくていい、額面は減ってない」っていう、親の安心料や。
10年後、子どもが大きくなって

パパ、僕のお年玉どうなってる?って聞かれたんや。ちゃんと10万円貯まってるでーってどやぁってしてやったわ。新しいゲーム買うみたいや。

待て待て。10年前のゲーム機、いくらやった?

3万円くらいやったな。

今はどんなもんや?

…3万5,000円。値上がっとる…。

それがインフレや。
お年玉のインフレ対策|今すぐできる3つの方法
1. インフレ分を親が補填する
これが一番シンプルで誰でもできる方法。
- 10万円に対して
- 毎年2%(2,000円)を親が足す
- 10年で約2万円の補填
これで「安心料」は親の財布から支払われる。月割りにすれば167円。まぁお手頃でしょう。
2. 使い道を一部決めておく
- 7万円:預金(安心枠)
- 3万円:家族体験(旅行・写真撮影など)、子どものための育児用品
思い出は目減りしない。むしろ時間とともに価値が上がります。出産祝いなどはベビーカーやチャイルドシートなどに使う人も多いのではないかしら。
3. 子どもと一緒に考える
小学生くらいから「お金の勉強」として一緒に管理。
- 物価が上がること
- お金の価値が変わること
- どう守るか
これこそ自身のお金を題材にしたリアルな学びになると思う。
子どものお年玉管理に正解はあるのか?
正直に言います。何が正解かなんて、誰にも分からない。
- 預金のままで目減り → まあ確実に額面は残る
- 何か行動して成功または失敗する → 両方の可能性がある
- 子どもに自由に使わせる → 未就学児くらいだと判断力まだ怪しい?
どれを選んでも、10年後に「あっちにすれば良かった」って思うかもしれません。
でも大事なのは、「知らずに選ぶ」と「知って選ぶ」は違う。
インフレで目減りすることを知った上で、あえて預金を選ぶならそれもOK。ただし、その時は自覚してほしい。
「私は心の安心料を、子どもの財布から払ってる」
まあ、実は合理的経済人であれば、メンタルアカウンティングが存在しないから、こういった葛藤は生じないんだけど、我々は普通の人間だからね。
まとめ|お年玉の預金管理で親が知っておくべきこと
- 子どものお年玉を「普通預金」に入れるのは、親の“安心料”構造
- インフレ2%で10年後には約1.8万円の価値が目減りする
- 親の“損失回避”は「子どものお金」になるとブーストされる
- 「減らしたくない」が「動けない」につながるメンタルアカウンティング
この構造に気づくだけでも、価値がある。あなたの安心料、月いくらですか?そしてそれ、誰の財布から出てますか?
少々厳しい視点を書いたけれども、少しでも心にドキっと来るものがあったなら、それはあなたが子どもを大切にしている証拠。
決して負い目を負うことじゃない。気づきがあったからこそ考えられる。考えた結果がどうであれ、その考えた行為こそが愛情でしょう?
おまけ|究極の解決策
子どもに聞いてみた。
私:「お年玉、どうしてほしい?」
子:「ポケモンカード、クレーンゲーム!!でっかいゲンガー取るんや!」
…やっぱり親が見守るのが現実的かもしれませんね(笑)。でも考えたら、インフレで目減りするより教育的か?
「お金は簡単になくなる」
これを10万円で学べるなら、安い授業料…。なわけ無いですね!もちろん冗談!
免責事項:本記事は一般的な情報提供・学習を目的としたものであり、特定の金融商品・投資行動を推奨するものではありません。実際のインフレ率や金利は変動します。家計や教育方針は各家庭で異なるため、必要に応じて公的情報や専門家の意見をご確認ください。
関連記事


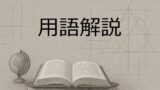
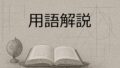
コメント