はじめに|トロッコ問題と『プライベート・ライアン』を哲学で読み解く
戦争映画の名作『プライベート・ライアン』を、哲学の視点から読み解いてみたい。この映画は、実はマイケル・サンデルが提起する『正義』の問題と深く共鳴している。
皆様、トロッコ問題という有名な思考実験をご存知でしょうか?
「トロッコの行き先に5名の作業員がいる、ブレーキは壊れこのままでは5名を轢いてしまう、別のルートに線路を切り替えればそこには1名の作業員がいる。切り替えれば1名を轢いてしまう。さて、あなたは線路の切り替えを行いますか?」
多くの方がご存知かもしれません。
この問いは「これからの『正義』の話をしよう」というマイケル・サンデル先生の書籍で紹介されている内容です。本文ではさらに細かい条件の変更等が書かれているのですが、今回は要点に絞って論じます。
このトロッコ問題を聞いたときに、私が想起したのはスティーブン・スピルバーグ監督による戦争映画の金字塔『プライベート・ライアン』でした。
ハリウッド映画と哲学書、一見無関係に見えるけれども、両者は道徳的哲学の根本を違った視点で提供していると見えました。今回はこの無関係に見える2つのコンテンツをクロスさせながら、書いていきます。
この記事でわかること
- トロッコ問題と『プライベート・ライアン』の構造的類似性:「多数を救うために少数を犠牲にする」という道徳的ジレンマの共通点
- 功利主義の視点:「最大多数の最大幸福」という考え方で映画を読み解くと、ライアン救出任務がいかに「非効率」に見えるか
- カントの義務論の視点:ミラー大尉の行動に見る「人間を手段ではなく目的として扱う」という道徳哲学の実践
- ライベン一等兵の心理的転換:功利主義的な疑問から義務論的な決意への変化を示す重要なシーン
- 現代社会への示唆:災害時のトリアージなど、私たちが直面しうる道徳的選択の問題
プライベート・ライアンのあらすじとトロッコ問題の比較
映画を知らない人のため、簡潔に内容を書くと──
第二次世界大戦ヨーロッパ戦線において、兄弟3人が戦死した1人の兵士を保護するために、8名の兵士が危険を犯し戦地を探す物語です。子ども3名を一度に亡くした母親の苦悩を鑑みての軍上層部の命令でした。
この簡単な一文だけで、トロッコ問題と結びつけられませんか?
- トロッコ問題:5名を救うのに、1名を犠牲にしてよいか
- プライベート・ライアン:1名を救うのに、8名を危険にさらしてよいか
これで両者の問いが整理されましたね。目的は手段を正当化するのかどうか、ということでしょうか。
功利主義とは?映画に見る「最大多数の最大幸福」
功利主義という言葉があります。「最大多数の最大幸福」を実現する行為が道徳的に正しい。ジェレミー・ベンサムが主張する考えです。「みんながハッピーになれるのならば、多少の犠牲はやむを得ない」という、結構ドライな考え方。
この考えに従えば、ライアン捜索の任務は明らかに「非効率」となります。8人の命を危険にさらして1人を救う。これは数学的に「赤字」でしょう。
トロッコ問題も、1名を犠牲にして5名を救え、というのが功利主義の結論です。
しかし、これで納得される方はごく少数では?
映画序盤では、8人のうち多くの兵士が、この功利主義を主張します。特に代表的なのはライベン一等兵。仲間の2人目が戦死した際、彼は上官である主人公に対してこう問いかけます。
俺達2人の命より、ライアンの命のほうが尊いのか!
軍隊の序列を考えれば、上官に対してこれほど感情をあらわにして発言することは異例。彼の中に相当な葛藤があったことを示していると思います。
この問いは映画全体を通じて繰り返し現れますが、ライベン一等兵の感情を顕に主張するシーンがピークですね。仲間たちに共通する功利主義が爆発する瞬間です。
カント義務論とは?ミラー大尉に見る「人間を目的として扱う」視点
対照的に、カントの道徳哲学に移ってみましょう。
カントの義務論では、行為の道徳性は「結果」ではなく、義務への純粋な意志によって判断されます。重要なのは「崇高な動機」という曖昧なものではなく、人間を常に手段としてではなく、それ自体を目的として扱うことです。つまり、ライアン一人の命も「効率」や「計算」では測れない絶対的な価値を持つ。その命を尊重すること自体が、道徳的に正しい行為とされるのです。
主人公のミラー大尉の姿勢は、この義務論に近い気がします。彼は任務を「命令だから」遂行するだけでなく、「正しいこと」だと信じている。そう思うことによって自分を納得させているのです。
上述のライベン一等兵が爆発したシーン、ミラー大尉はこうしてその場を収めます。
ライアンなんてどうでもいい。ただの名前でしかない。ただ、彼を救出して故郷に返せれば、胸を張って妻のもとに帰れる気がする。
ミラー大尉の言葉には、カント的な道徳観の影が見えます。自身の道徳観を充足することで、家族に誇れる姿を見せようとしている。
さらに、カントの義務論における重要な概念として「定言命法」があります。これは「自分の行動の原則が普遍的な法則となることを望むように行為せよ」というもの。普遍的な法則=人間は皆尊く尊敬に値する、というところでしょう。ミラー大尉の決断はまさにこの定言命法に則っているように見えました。 もちろん、違った解釈も可能でしょう。「忠誠」「友愛」といった軍人にしかわからない世界があるのかもしれない。
ライベンの頷き|功利主義から義務論への転換点
映画では、ライアン救出チームは軍事上重要な橋の近くでライアンを見つけます。
命令通りライアンを連れて帰りたいところですが、ライアンは仲間と一緒にここで橋を守ると主張。ライアンもカントのごとく仲間を尊く扱い、見捨てられなかったのでしょう。「自分が生き残る結果」よりも「仲間と戦うという動機」のほうが彼のなかで重要だった。
そこで救出チームは橋の防衛に加わることにしました。
敵軍を待ち伏せするシーンにて、上述のライベン一等兵が、ライアンをじっと見つめてから頷く場面があります。無言のシーン。
私はここに、功利主義から義務論への転換を見ました。ライベンは功利主義の顔として描かれてきましたが、このシーンは様々な解釈ができる。
- お前(ライアン)のせいで仲間が複数死んだという恨み(功利主義)
- ここでお前を助けないと、死んだ仲間が浮かばれない(サンクコスト的思考)
- 意地でもお前を故郷に連れて帰る、それが俺の任務だ(カント的動機)
どれもあり得ますが、私は3番目だと思っています。
つまり、頷きは「効率」や「計算」を超えた承認であり、「こいつを絶対に故郷へ返す」という道徳的決意を示す瞬間に見えた。功利主義から義務論に心を委ねる瞬間に見えたのです。
もちろん、この解釈は映画を見た人それぞれで違うでしょう。
現代に生きる私たちへの問い
この問いは決して映画の中だけの話ではありません。例えば、災害時のトリアージ(誰を優先的に治療するか)では、似たような状況に直面することもあるでしょう。
果たして、万人が納得する答えを我々は用意できるでしょうか?
結論|功利主義と義務論の問いは映画でも終わらない
『プライベート・ライアン』を哲学書として読むと、映画の見え方が変わります。ただの感動的な戦争ドラマではなく、道徳哲学の古典的対立──功利主義と義務論──を体現した物語として見えてきませんか。
サンデルとスピルバーグは、異なるメディアで同じ「正義とは何か」という問いを投げかけている。そしてどちらも、その問いに明確な「答え」を用意していない。単一の正義などこの世に無いからでしょう。
あなたはライベンの頷きに、どのような意味があると考えますか?ぜひご意見を頂戴したいです。
関連記事
ゲーセンに哲学を持ち込んだ、ちょっと異質な記事は以下。



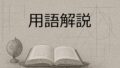
コメント