はじめに|子育てで撃沈する
普段は「構造」や「メタ」を真顔で語っている米田ですが、実はごく普通の子育て中の親父でもあります。
この連載「予想以上に不合理」では、親が理論武装して子どもの行動を分析しようとしても、あっさり打ちのめされる様子をお届けします。
タイトルはもちろん、行動経済学の名著『予想通りに不合理』(ダン・アリエリー)へのオマージュ。
世のママ・パパたち、一緒にこの“不合理な日常”を笑い飛ばしていきましょう。
この記事でわかること
- なぜ注意しても子どもは水たまりに飛び込むのか
- フレーミング効果・プライミング効果が生む親子のすれ違い
- 発達心理学から見た「子どもには合理性が通じない」理由
- 水たまりダイブを減らす実践的な2つの対策
- 「洗濯物=思い出の代金」という新しい考え方
ソコミズタマリ!アッー!!
未就学児から小学校低学年を育てたことがある方なら、思い出しただけで胃が痛くなるフレーズ。
「ソコミズタマリ!アッー!!」そう、水たまりダイブです。
雨上がりの散歩と不穏な注意喚起
雨の日、子どもはレゴやYouTubeでなんとか持ちこたえるものの、親も限界。 やっと雨が上がった! これは散歩のチャンス。お気に入りの長靴を履かせて出発。
親は言います。
「水たまりに気をつけてね」
「はーい!」
……はい、もう展開は読めますね。
水たまりへの全力疾走
道路の端にキラキラ光る大きな水たまり。次の瞬間、子どもは100m走のスタートダッシュ。
「ソコミズタマリ!アッー!!」
親の制止もむなしく、ジャブン。長靴の中は瞬時に水没、靴下びしょ濡れ。親の頭の中では「洗濯物が増えた…」と損失計算が走ります。
なぜ長靴を履いても水たまりに飛び込むのか【フレーミング効果】
フレーミング効果とは、同じものでも「見方の枠組み(フレーム)」が変わると、全く違う意味を持ってしまう心理現象です。
マーケティングでは「成功率90%」と「失敗率10%」の言い回しの違いなどが有名ですね。
この原理は、長靴にも無理くり当てはめてみます。
- 親のフレーム:長靴は防具。水から足を守る道具。
- 子のフレーム:長靴は武器。水たまりに突撃するための必殺アイテム。
同じ長靴でも、枠組み次第で意味は真逆。なんなら長靴はエクスカリバー。
親は「守ってあげよう」と思って渡したのに、子どもは「攻めに行ける強化装備」だと信じて疑わない。
このズレこそが、水たまりダイブを生み出す根本原因ではないでしょうか?
「気をつけて」が逆効果になる理由【プライミング効果】
さらに厄介なのはプライミング効果。「水たまりに気をつけて」と言った瞬間、子どもの頭には水たまりのイメージが鮮明に浮かびます。
大人だって、「〇〇を見るな」って言われると逆に視線を送っちゃうこと、あるでしょう?
良かれと思った注意喚起は「水たまりへの招待状」に早変わり。せっかくリスク回避を狙った言葉が、逆にリスクへの道を開いてしまう。親の善意がブーメランのように返ってくる瞬間です。
子どもに論理が通じないのは当たり前【ピアジェの発達心理学】
さらに発達心理学の観点から見ると、この行動は極めて自然。
ピアジェの理論で言えば、未就学〜小学校低学年は「感覚運動期〜具体的操作期」。この段階では、未来の因果関係や他者の視点を十分に扱えません。
親は「靴下が濡れる → 後で冷える → 風邪をひく → 洗濯物が増える」と合理的因果を描きます。
でも子どもにとっては「チャプチャプ楽しい!」で完結。要するに、親の合理は子どもの世界にインストールされていないのです。
だから「洗濯大変になるからやめて!」と言っても、「知ったこっちゃない」わけです。
2つの心理のせめぎあい【現在バイアス vs 損失回避】
行動経済学的に見ると、ここには心理的すれ違いがあります。
- 子ども:現在バイアス 未来の不快よりも今すぐの快楽を優先。
- 親:損失回避 楽しみよりも「洗濯物が増える」という損失の痛みを強く感じる。
つまり、親子で真逆のバイアスに動かされている。これでは意思疎通が成立しないのも当然です。
実践的対策|親のサバイバル術
対策はないのか
ここまで理屈をこね回しましたが、現場の親には即効性のある対策も必要です。
実際に試して効果があった(ような気がする)方法を二つ紹介します。
- 水たまりジャンプで飛び越えさせる 「今日は忍者修行や!」とフレーミングを転換。 飛び込むのではなく飛び越える遊びにすり替えると、ダイブ率が多少下がる。
- 諦めて着替えを持参する もうこれは損失回避を放棄して、コストを織り込んでしまう作戦。 「洗濯物が増える=思い出の代金」と割り切って、濡れてもOKな装備で出かける。 精神衛生上はこれが一番ラク。濡れた服をいれる袋もお忘れなく(笑)
実践レポート

この前、「水たまり」って言葉を使わんようにしてみてん。意識させないようにな。

お、ついに実験やな。どうやった?

「今日は忍者の修行や、隅っこを歩いて行くで」ってフレーミングして出かけたんや。

ほう、意味づけの転換やな。やるやないか。結果教えてや?

最初はうまくいってた。コソコソ歩いて追ったで…

でも?

最後の最後で「忍者も時には水遁の術を使う!」言うて、結局ダイブ(笑)

子どもの創造力、恐るべし(笑)。たしかに水遁の術使うな。子どもの圧勝や
期間限定の特権と思ってみる

でもな考えてみ、大人が水たまりに飛び込んだらどうなる?

変な人と思われる(笑)。なんなら離れて歩かれるな。

せやろ?つまり、水たまりダイブは子ども時代の期間限定特権なんや。誰も小さい子供が水たまり入ってても文句言わへんやろ?むしろ微笑ましく見てもらえるわ。

確かに…中学生でもやらへんもんな。中学生なら服濡れるほうが嫌がるな。

そうや。そう考えたら、多少の洗濯物くらい、思い出の値段としては安いかもしれへんな。一歩引いて動画で撮っておく位の親の度量があっても良いのかもしれへん。
まとめ|構造を知れば、少し優しくなれる
水たまりダイブを通して見えてきた構造:
- 親の視点:損失回避(洗濯物)が行動を支配
- 子の視点:現在バイアス(今の楽しさ)が全て
- すれ違いの原因:フレーミングの違い+発達段階の限界
結論:理論で説明できても止められない。でも構造を知れば、イライラが「まあしゃーないか」に変わる。それが、この連載「予想以上に不合理」でお伝えしたいことです。


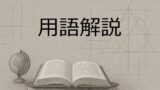


コメント