はじめに|夫婦の永遠のテーマ「家事分担」
「私のほうが家事やってる!」
このフレーズ、夫婦喧嘩ランキングの上位に必ず食い込みません?掃除、洗濯、炊事、子どもの世話…。皆さんのお宅では、それぞれどれくらいの割合で分担していますか?
一度、こうして考えてみてください:
- 掃除:◯%
- 洗濯:◯%
- 炊事:◯%
- 子どもの世話:◯%
あるいは、もっとシンプルに「家事全体を100%として、自分は何%やっているか?」でも構いません。同じ質問をパートナーにもしてみましょう。ただし、お互いの回答は見ないように。
答えを足し合わせたとき、合計が100%を超えていませんか?もしそうなら、そこには心理学的なからくりが潜んでいます。
利用可能性ヒューリスティックとは?夫婦の家事あるある
行動経済学には「利用可能性ヒューリスティック」という現象があります。簡単に言うと、思い出しやすい情報に過度に依存して判断してしまう傾向です。
- 俺は昨日、晩ごはんを作った。
- 私は毎日洗濯をしている。
- 俺は毎週ゴミ出ししている。
- 私は子どもの迎えをよくしている。
こうした記憶は、すべて「私がやったこと」。自分の行動は鮮明に覚えている一方、相手がしてくれたことは霞んで見えがちです。
その結果、「私のほうが家事をやっている」という認識が強まるのです。ちなみに、飛行機事故のニュースを見た後に「飛行機は危険だ」と思い込むのも同じ仕組み。実際には交通事故の方が圧倒的にリスクが高いのに、印象的な出来事に引きずられてしまうんですね。
この現象、実は心理学者でノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンも 著書『ファスト&スロー』で夫婦の家事分担を例に説明しています。 世界的な行動経済学者が認める、まさに「夫婦あるある」なんですね。

えー、でも実際俺のほうが家事やってるやん!昨日も皿洗いしたし!

それが利用可能性ヒューリスティックやで。自分の行動は100%記憶に残るけど、相手がやったことは0%に近く見えるんや。

じゃあ、ほんまの分担ってどうやって分かるん?

1週間記録したら見えてくる。でもな、正確な数字より大事なのは「相手の貢献をちゃんと認識すること」や。
反対意見への配慮|本当に偏っている場合もある
ここで「いやいや、実際にめっちゃ偏ってる家庭もあるやん!」という声もあるでしょう。その通りです。利用可能性ヒューリスティックは“認識のズレを生む一因”であって、すべてのケースを説明する魔法の理論ではありません。だからこそ、まずは現状を「見える化」することが大切です。
- ざっくり家事リストを出し合ってみる
- 1週間だけ記録をとってみる
そこから「認識のズレ」が原因なのか、「実際にバランスが悪い」のかを切り分けられます。
理解してから理解される|7つの習慣のヒント
ここで役立つのが、スティーブン・コヴィーの名著『7つの習慣』。第5の習慣に「理解してから理解される」があります。自分のことを理解してほしいなら、まずは相手を理解すること。
夫婦間でもまさに当てはまります。1週間、パートナーがしている家事を意識して観察してみてください。
- いつの間にかシャンプーが補充されている
- 洗濯物がいつも畳んである
- 知らないうちにクリーニングが出されていた
こうした「見えない貢献」に気づくことが、最強の喧嘩回避策になるのです。
意外と見えていない家事のチェックリスト(我が家の実例)
- 洗剤や調味料等の在庫管理
- 洗濯槽の掃除
- 排水口の掃除
- 子どもの爪切り
- 子どもの予防接種の予約
言われてから「ああやってくれていたんだ」と気付かされた内容ですね。お恥ずかしい話。
子どもへの影響|夫婦関係と発達の研究
夫婦間の不和が子どもに影響することは、多くの研究で指摘されていますね。正直、私も両親が喧嘩をしていたシーンは大人になっても思い出すことがあります。あまり良い記憶ではありませんね。
しかし、親同士が理解し合い、喧嘩が減ることで子どもは安心する──私は心理学の専門家ではありませんが、直感的にも実感できる流れです。子どもにとって最も頼りにしている2人が仲良くタッグを組んでいたら、これ以上心強いことはありませんよね。
心理学には「モデリング効果」と呼ばれる概念があります。子どもは親の行動を無意識にまねるのです。つまり「夫婦のありがとう合戦」は、そのまま「子どものありがとう習慣」に変換される最高の教材といえます。
まとめ|幻を見る前に「ありがとう」
夫婦間の「私のほうがやってる」問題。その裏には、利用可能性ヒューリスティックという心理的なからくりが潜んでいるかもしれません。自分の行動は100%覚えているけど、相手の行動は0%に見える──だから合計が120%になってしまう。
このズレを修正する第一歩は「理解してから理解される」。今日から始められる行動をお伝えしましょう。
「相手の見えない家事を1つ発見しましょう。そしてその事に対しありがとうを言う」
相手の行動に目を向けること、そして最後に伝えるべき魔法の言葉は「ありがとう」です。夫婦が「ありがとう合戦」を始めたら、家事分担の不満は消えていくと思いますがいかがですか?
そしてその姿を見た子どもが「ありがとう」を口グセにしたとき──家事分担バトルは完全勝利です。


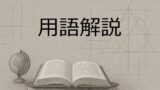
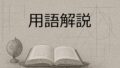

コメント