公園に行く前の「荷物問題」はなぜ起こる?
近所の公園によく子どもと遊びに行きます。かなり大きな公園で、ストライダー、自転車、虫取り、ちょっとしたボール遊び、何でもできるところです。 散歩がてら歩いていくことも多いのですが、子どもと公園に行く準備をしていると、毎回のように始まるやり取りがあります。
「これも持っていく!」「あれも必要!」
気づけば玄関にはストライダー、ボール、虫取り網、バドミントン…。
小旅行かと思うほどの荷物が山積み。ため息まじりに「本当に全部いる?」と聞いても、返ってくるのは断固たる一言。
「絶対に必要!」
なぜ子どもは荷物を増やしたがるのか?そしてなぜ親は「またか…」と疲れてしまうのか?
実はこのやり取りの裏側に、行動経済学の代表的な心理──損失回避が潜んでいるのです。
この記事でわかること
- 損失回避とは?:人は「得をする喜び」より「損をする痛み」を強く感じる心理。
- 子どもが荷物を増やしたがる理由:「遊びを逃す損失」を避けようとする、行動経済学的な本能。
- 親子で異なる”損失の基準”:子どもは「楽しみの損失」を避け、親は「体力の損失」を避ける。
- 年齢で変わる”失いたくないもの”の正体:3歳・5歳・7歳で異なる「持っていきたい理由」。
- 明日から使える、公園荷物問題の対処法:泣かずに、怒らずに、うまく「荷物を減らす」4つの工夫。
子どもの荷物と損失回避の心理
損失回避とは?行動経済学の基本
1000円を得たときの嬉しさより、1000円を失ったときのショックの方が大きい。
人間は「得たい」以上に「失いたくない」で動く生き物なのです。ノーベル経済学賞を受賞した、ダニエル・カーネマンの主張する、プロスペクト理論の一部です。
この原理を当てはめると、子どもの「荷物持っていく!」という主張がぐっと理解しやすくなります。
子どもにとっての最大の損失は「遊びを逃すこと」
ある日、公園に虫取り網と虫かごを持たずに行ったときのこと。たまたま子どもの友達たちが楽しそうに虫取りをしていました。
「自分もやりたい!」と訴えるわが子。でも道具がない。結局ただ後ろで眺めるしかなく、とても悔しそうでした。
その経験以来、「公園に行くなら虫取り網持った?」と必ず確認するように。
つまり子どもにとって最大の損失は、「遊びに参加できないこと」。その痛みを二度と味わいたくないからこそ、荷物を増やしてでも持っていこうとするのです。
親子で違う損失回避の基準
一方で、親にとっての損失は「荷物で体力を消耗すること」。
- 子ども → 楽しみを逃すことが損失
- 親 → 重い荷物で疲れることが損失
同じ損失回避でも、守ろうとする対象が真逆なのです。だから「持っていく」「やめとこう」で毎回ぶつかるのは必然。親が「重いの持つのはパパやで?」と訴えても、子どもの優先順位では下の方。
子どもにしてみれば、
「パパが重いとか知らん!遊べなかったほうがよっぽど損やん?」
くらいの感覚です。
これは児童心理学者ピアジェのいう「自己中心性」の段階そのもの。未就学児くらいでは子どもは自分の視点が世界の中心なので、他人の都合は考慮に入りません。
──つまり「パパは筋トレ担当でよろしく!」は、実は学術的にも正しい主張なのです(笑)。
公園荷物問題の解決策4選
1. 「持つなら自分で持つ」ルール
持ちたいものがあるなら、自分で運ぶことを条件に。虫取り網や砂場セットから始めれば、「荷物が多いと大変だ」という体験ができます。
2. あえて断る勇気
「持って!」と泣きつかれても、あえて断る場面を作る。自分で抱える苦労を知れば、次回のリストは自然に減るかもしれません。(もちろん体力や年齢に応じた加減は必要ですが)
3. 現地調達で「損失感」を薄める
公園には松ぼっくりやどんぐり、木の枝など、自然のおもちゃが豊富です。現地で夢中になれば、「持ってこなかった損失」は意外と感じません。
子どもがそこまで視野が広がらなければ、親が呼び水となることも重要。松ぼっくり探しするの、おすすめですよ。遊びのファシリテーターですね。
4. 親の合理的投資
結局担ぐことが多いなら、軽量モデルのストライダーを選ぶのもいいかも。うちは重たいの買ってしまったけれども、「子どものため」ではなく「親の体力を守るため」の投資もありだと思います。
ストライダーを抱えて1時間歩いた経験のある親御さんなら、わかってくれるはず。
親のリアルな心の声〜損失回避の裏側〜
子どもの「損失回避」に付き合う親にも、実は複雑な心理があります。
「また荷物増やすの…」と思いながらも、心のどこかで「まあ、楽しそうに遊んでくれたらいいか」と考えてしまう。これも実は親自身の損失回避です。
- 子どもが「持ってくればよかった」とグズるのを見たくない
- せっかくの休日を台無しにしたくない
だから結局「はいはい、持っていこうね」と折れてしまう。でも冷静に考えると、ストライダー担いで1時間歩くのと、子どもがちょっとグズるのと、どっちが損失大きいんでしょうね?
「子どもの笑顔はプライスレス」──そう自分に言い聞かせながら、ストライダーを担いでいた親父なのでした。そこから自転車になったらずいぶん楽でした!
年齢で変わる「失いたくないもの」
子どもの年齢によって「避けたい損失」も変わりますね。執着するものが年齢で変化していきました。
- 2〜4歳:所有欲の芽生え期 :「MY虫取り網」「MYボール」を持つことで安心感。荷物は「自分の装備」。だから、ボールはボールでも「MYボール」でないとグズるんですよね。
- 5〜6歳:社会性の発達期 :仲間に入れないことが最大の損失。「みんな持ってるから」が理由になる。うちの子どもの虫取り網はこちら。
- 7〜8歳:効率を考え始める時期 :「重い」「邪魔」と感じ始めるが、「念のため」精神はまだ健在。 ただし「自分で持つ約束」をすると急に荷物が減る。少しずつ違った損失が見始めますね。
思い返すと、「わかる!」って人多くありませんか?この変化を知っていると、「今はこういう時期なんだな」と少し優しい目で見られるかもしれません。

なるほどなぁ。何を損失と感じるかなんて、人それぞれやもんな。子どもが親の視点をもてというのは無茶やから、親が合わせてやらんとあかんな。

せやな。どっちが力関係が強いかなんて明らかやからな。親の視点を押し付けたら、そりゃグズるて。子どもは自分の”世界の中心”から見てるだけや。
大人も同じ?損失回避の「荷物癖」
子どもだけでなく、大人も似たような行動をしていますね。
- 使わない折り畳み傘を一日中持ち歩く
- 結局使わないモバイルバッテリー
- 2年着ていない服を「いつか着るかも」と残す
- 期限切れのポイントカードを財布に入れっぱなし
どれも「なかったら困るかも」という損失回避の心理。……どうですか?ひとつくらい心当たり、ありますよね?
ギクッとした方は、ストライダー担いで筋トレしておきましょう(笑)。
まとめ:公園は損失回避を学ぶ実験場
- 子どもは「楽しみを逃す損失」を避けたい
- 親は「体力を消耗する損失」を避けたい
- 同じ損失回避でも、守っている“価値”が違う
- 年齢が上がると、守りたいものも変化する
- 公園は、損失回避を“体感で学べる”実験場
同じ損失回避でも、守っているものが違うからこそ衝突する。でもその違いを知れば、歩み寄りのヒントにもなります。
次回公園に行くとき、子どもの「持っていきたい!」に耳を傾けてみてください。子どもが守ろうとしている楽しみが見えてくるはずです。そして気づくでしょう。
不合理なのは子どもだけでなく、大人も同じだと。
おまけ:やっぱり不合理な子ども
その後公園に行く際、子どもに聞きました。
「ストライダー持っていくでー?」
返ってきた答えは──
「今日は疲れてるからいらん!」
……やっぱり予想以上に不合理でした。


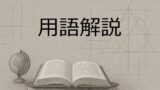

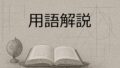
コメント