導入|先日は取れたのに、今日は全然あかん──子どもの「ゲーセン現象」
うちの子、ちょっとショッピングモールに行こうものなら、すぐに「ゲーセン行きたい!クレーンゲームしたい!」と言います。
まあ楽しみのひとつとして、少しだけお小遣いを渡すわけです。「まあ取れないだろうけど、楽しみの対価や」と思いながら。
ところが──ときどき親の想像を超える出来事が起こります。
まさかの一発ゲット。
ぬいぐるみを抱えて、ウキウキで自慢してくる。けれど、当然その逆もある。
何度やっても取れず、しょんぼりして帰ってくる日。
運が良い日もあれば、どうやってもダメな日もある。でも結局、トータルで見ると「お金に対する景品の取れ方」って、だいたい似たような水準に落ち着く。
親御さんであれば、きっと一度は経験しているこの現象。
実はこれ、「平均回帰(Mean Reversion)」の好例なんです。では、この“普通に戻る力”──平均回帰の仕組みを、もう少し詳しく見ていきましょう
この記事でわかること
- 平均回帰とは何か
ゴルトンが発見した「極端な結果はやがて平均に戻る」法則
- カーネマンが暴いた“錯覚”
イスラエル空軍の事例で明らかになった、「叱ると伸びる」「褒めると下手になる」が勘違いである理由。
- 日常で働く平均回帰の構造
- 行列ラーメン屋のブームが落ち着くメカニズム
- 子どものテスト点数が安定していく理由
- ゲーセンの「取れやすい店」都市伝説の正体
- 異常に高い平均
平均回帰の法則を超えたように見える「例外」が、実は平均値そのものの高さで説明できること。
- 今日から使える“平均回帰の知恵”
浮き沈みに一喜一憂せず、「自分の平均値」を少しずつ上げるための実践的ヒント。
平均回帰の意味と定義(辞書的解説)
平均回帰(Mean Reversion / ミーンリバージョン)とは、極端な値が時間の経過とともに平均値に近づいていく現象を指します。
この概念を最初に示したのは19世紀の統計学者フランシス・ゴルトン。
極端に背の高い親を持つ子どもは、親ほど背は高くなく、極端に背の低い親を持つ子どもは、親ほど低くない。それぞれ平均的な身長に近づく傾向を観察した。つまり「極端」は次世代で薄まり、平均に戻ることを発見しました。
さらに心理学者ダニエル・カーネマンは、著書ファスト&スローでイスラエル空軍の指導現場における”平均回帰の誤解”を紹介しています。
日常例でわかる平均回帰|ラーメン屋と子どものテスト
行列のできるラーメン屋とその収束
駅前に新しいラーメン屋がオープンしたとしましょう!大変美味しいと口コミで評判とします。
- 開店直後:1時間待ち
- 1ヶ月後:30分待ち
- 3ヶ月後:10分待ち
- 6ヶ月後:近所の店と同じくらい
結局、味・立地・価格といった「実力」に客入りは収束していきます。これが平均回帰。
一時的なブームが消えた後に、本当の実力=平均値が見えてくるのです。
さらにラーメンは価格でも平均回帰が働きます。
- 1杯2000円の超高級ラーメン → 話題性はあるが、長期的には固定客しか残らない
- 1杯300円の激安ラーメン → 一時的に人気でも、原価や品質の壁で持続しにくい
最終的には、多くの店が700〜900円前後の「普通の価格帯」に落ち着くでしょう。
これもまた、市場全体で働く平均回帰の一例なのです。
子どものテスト点数の推移
- 100点!「天才かも」
- 75点…「あれ?」
- 85点「まあまあ」
- 80点「安定」
- 90点「いい感じ」
- 85点「これくらいかな」
平均すると約86点。これがその子の実力値。100点は上振れ、75点は下振れ。どちらも一時的で、結局は平均に戻る。
親としては「この86点をどう積み上げて90点ラインに平均をシフトさせるか」を意識するのがポイントですね。
ゲーセンで見る平均回帰|関連記事とのつながり
前回のゲーセン経済記事で「取れやすい店の都市伝説」について触れました。「新規オープンは取れやすい」という噂、これもまさに平均回帰。
- オープン直後:設定甘い → SNSや口コミ拡散 → 客殺到
- 1ヶ月後:客単価下がる → 利益圧迫 → 設定調整開始
- 3ヶ月後:普通の店と同じ設定に収束
極端な「取れやすさ」も、時間が経てば普通に戻るんです。
カーネマンが解いた誤解|叱ると伸びるは錯覚?
ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンは著書『ファスト&スロー』の中で、パイロットの訓練の有名な逸話を紹介しています。
あるとき教官がこう主張しました。
「良い操縦をして褒めると次は下手になる、悪い操縦をして叱ると次は上手くなる。だから叱る方が正しい」
カーネマンは即答。「それはただの平均回帰です」
- 特別に良い成績 → 褒めても次は普通に戻る
- 特別に悪い成績 → 叱っても次は普通に戻る
教官は自分の指導力と勘違いしていただけだったのです。 これは当初読んだときには目から鱗が落ちました。私も子育てに応用させてもらってます。
褒める意味は「自己肯定感や学習意欲を育てて、平均点そのものを上げること」にあります。
逆に叱る意味も「ピットフォールなどを指摘して、平均点を上げること」。
両者目的は一緒です。短期的な結果に満足せず、対象の「平均値」を見てあげればいいということですね。親の観察眼が問われます。
平均の推移を理解する|移動平均という考え方
日々の変動に一喜一憂せず、全体の流れを掴むには移動平均が役立ちます。移動平均とは過去一定期間の平均値を区間をずらしながら計算し、長期的な傾向を把握する手法ですね。
1日ごとの増減を気にするより、過去7日間の平均値を記録してグラフで見れば、ゆるやかな傾向が分かる。 売上など日々の「ノイズ」が多い領域では、本質的なトレンドを見るのに移動平均は非常に有効です。
平均値が異常値|イチローの場合
本記事を書きながら日本プロ野球時代のイチロー選手を私は思い出していました。普通なら打率.380打った翌年は多少成績は落ちる。
でもイチローは.340。なぜ?
答え:イチローの平均がそもそも打率.360前後。
不調の年でも首位打者という、もはや平均回帰のバグか?と思いたくなりますが、平均回帰です!上振れも下振れもあるけれど、回帰先が常人離れしてただけなんです。
打率.340で「今年は調子悪い」となるのは、平均が高すぎるがゆえの現象。つまり平均回帰の法則を超越したわけではなく、「普通」が異常に高かっただけなのです。

駅前のラーメン屋、行列なくなったな

味が落ちたんやなくて平均回帰や。『新しさ』は必ず消える。残るのは『実力』だけや。最初はどうしても話題性が勝つな。1年経過してからがホントの実力ちゃう?

子どもが100点取ったのに次は75点…。100点のときえらい褒めたからな。やりすぎてもうたか?

カーネマン案件や。平均に戻っただけやろ。そのまま様子みてあげてや?ブレながらも右肩上がりが一番大事で。

じゃあイチローは?調子悪いシーズンで首位打者って、どうにかしてるやろ。

あれは平均が異常に高かったんや。淡々と努力する天才やで?。努力でとんでもない平均値を叩き出してたんや
まとめ|平均回帰は残酷で優しい
- 特別は続かない。奇跡もやがて”普通”に戻る。でも、それは失敗も同じ。落ち込みも長続きしない。
- 「平均に戻る」仕組みを知れば、誤解しなくなる。叱って伸びた・褒めて落ちた──それは指導力じゃなく確率の話。
- 平均回帰は”残酷”だけど”優しい”法則。極端を責めず、長期的な実力(平均)を見れば、焦らず成長できる。
- 今日の教訓:一喜一憂せず、自分の平均を上げていく。短期の浮き沈みはノイズ。上げたいのは「平均値」そのもの。
大事なのは一喜一憂しないこと。「自分の普通」を少しずつ上げること。
浮かれず、落ち込まず、淡々と。これが行動経済学が示す最も確実な成長戦略です。

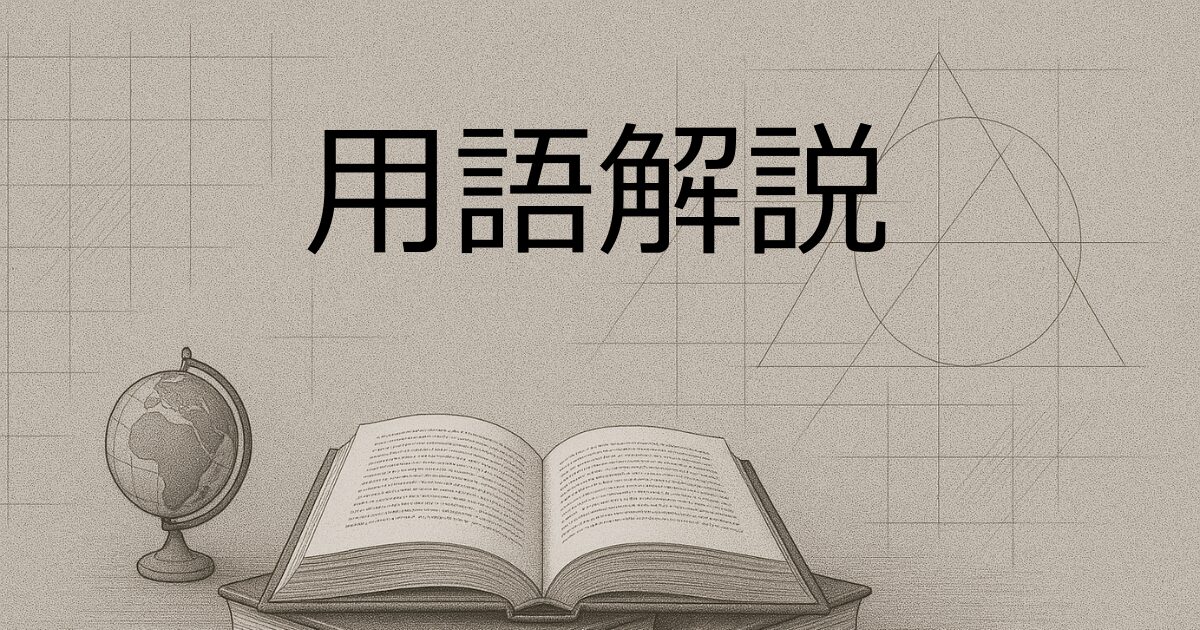


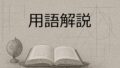
コメント