プロローグ|うっかり構造に囲まれた日常
10年以上も前でしょうか、ネットでちょっとした買い物をしたんです。後日メーラーには「セール開催!」「期間限定!」「残りわずか!」のタイトルでメールがズラリ。思わず心の中でつぶやきました。「なんやねんこのメール・・・」
恐らく皆様ご経験あるでしょう。メルマガ送付チェック外すの忘れたら、翌日からメルマガ爆撃。
他にも、クレジットカード申し込んだら自動リボ設定がデフォルトでONになってる。
パソコンでアプリのインストールをしてみたら、別のアプリまで一緒に入ってる。
また別口ですが、とある行政の補助金の申請をしよう思って行政のホームページで書類探したけど、まあ見つからない。ようやく見つけたと思ったら、今度は添付書類が必要って書いてあって、その添付書類のフォーマットがどこにも見当たらん──。
もう笑うしかない。
実は、これらのエピソード、根底には同じ構造が隠れています。この記事では、その構造を解きほぐしていきます。
この記事でわかること
- ダーク・コマーシャル・パターンがナッジの構造を”利益の方向”にねじ曲げる仕組み
- 行政スラッジが生まれる背景と、善意が詰まりを生む理由
- スラッジとナッジの構造的な違い(目的・自由の実質性・心理効果の方向)
- 日常で遭遇するスラッジの具体例(メルマガ爆撃・解約迷路・申請手続の煩雑さ)
難しく聞こえるかもしれませんが、実は身の回りにあふれている話。 一緒に「詰まりの構造」を読み解いていきましょう。
はじめに|「良いナッジ」が「悪いスラッジ」に変わるとき
プロローグのエピソード、実はこれ、「スラッジ(sludge)」と呼ばれる現象です。 人の行動を”そっと後押し”するナッジの裏側で、逆に人を”詰まらせる”設計のこと。
スラッジとは?|“詰まり”を生むナッジの裏側
ナッジ(Nudge)は、人の行動を「そっと後押し」する仕組み。たとえば、階段をピアノの鍵盤にして上りたくなるようにしたり、健康的な食べ物を目の高さに置いて“つい選ぶ”ようにする設計です。でも、その仕組みが逆方向に働くこともあります。
それが──スラッジ(sludge)
ノーベル経済学賞を受賞したリチャード・セイラーは、2018年の論文 “Nudge, not Sludge.” の中でこう述べています。
「ナッジは行動を助ける設計、スラッジは行動を妨げる設計である。」
つまりスラッジとは、人の自由を形式上は残しつつ、実質的には“動けなくしてしまう”設計のこと。

「”助ける設計”が”詰まらせる設計”に変わるって、どういうことなん?」

「たとえば、サブスクの”解約ページが見つからん”とか、行政の”申請フォームが複雑すぎる”とか。行動コストが上がって”やる気が削がれる”設計や。」

「あー、あれか。めんどくさくて”また今度”ってなるやつ。」

「せや。”今度”はだいたい来ぇへん。それが”スラッジ”が生んでる行動の詰まりや。」
スラッジの構造|「意図的」と「非意図的」に分かれる
スラッジには大きく2つのタイプがあります。
| 種類 | 目的 | 主な特徴 | 例 |
|---|---|---|---|
| 意図的スラッジ | 利益・操作目的 | 利用者の摩擦を“設計”している | サブスク解約迷路、誤操作誘導 |
| 非意図的スラッジ | 義務・透明性・正確性の追求 | 善意の仕組みが逆に行動を阻害 | 行政HPの過剰情報、申請手続の煩雑さ |
どちらも共通しているのは、「行動コスト>行動意欲」になってしまう構造。

「ほな、悪意があるやつも、悪気ないやつもあるってことか。」

「そうや。前者は”ブラックナッジ”みたいなもんやけど、後者は”正義が詰まりすぎたスラッジ”や。」

「なるほどな。悪気ないのに人を動けんようにしてまうのも、構造のせいか。」

「せや。”今度”はだいたい来ぇへん。それが”スラッジ”が生んでる行動の詰まりや。」
ダーク・コマーシャル・パターンとは?|OECDが警告する“意図的スラッジ”
スラッジの中でも特に、企業が消費者の心理を意図的に利用して利益を得る設計をOECDは「ダーク・コマーシャル・パターン(Dark Commercial Patterns)」と呼んでいます。
2024年のOECD報告書では、オンライン上の取引やアプリ設計で、「自由は形式上あるのに、実質的には選ばされている」ケースが世界的に拡大していると警鐘を鳴らしています【OECD, 2024】。

「”自由に選べる”って言うけど、実際には”そう選ばされてる”ってこと?」

「そう。ナッジの”そっと後押し”を、利益のために”そっと誘導”に変えとるんや。OECDはこれを7つの型に分けて分析してるで。」
OECDの7区分|ナッジを“歪める”7つの構造
| 区分 | 概要 | 日常の例 | 働く心理バイアス |
|---|---|---|---|
| 1. 行為の強制(Forced Action) | 不要な個人情報の開示や登録を事実上強いる。 | 無料トライアルを始めるのにクレカ登録が必要 | 選択回避バイアス |
| 2. インターフェース干渉(Interface Interference) | デザインや配置で、特定の選択を取りやすく見せる。 | 「おすすめプラン」だけ派手な色で表示される | フレーミング効果/注意の有限性 |
| 3. 執拗な繰り返し(Nagging) | 拒否しても同じ行動を繰り返し促す。 | 「通知ONにしませんか?」が何度も出る | 単純接触効果 |
| 4. 妨害(Obstruction) | 解約や退会など“望ましくない行動”を不必要に面倒にする。 | 解約ページが深い階層に隠されている | 認知的疲労 |
| 5. こっそり(Sneaking) | 料金や条件を目立たない形で追加・抱き合わせにする。 | 無料ソフトに別アプリが自動でインストールされる | サリエンシー効果の操作 |
| 6. 社会的証明(Social Proof) | 他人の行動や評価を強調して安心感・同調を誘う。 | 「他のお客様の声」「高評価レビュー」が強調表示される | 同調バイアス/社会的承認欲求 |
| 7. 緊急性(Urgency) | 時間や在庫の少なさを強調して即決を促す。 | 「残り3点」「あと5分で終了」と表示される | 希少性ヒューリスティック |

「”残り3点”とか”あと5分”とか、まんまと焦らされて買ったことあるわ…。」

「それ、”緊急性ナッジ”をブラック化させた典型や。本来は意思決定を助ける仕掛けやのに、焦りを利用して”考える暇を奪う”構造になっとる。」

「そう聞くと、結構こわいな…。」

「OECDの報告でも、”ナッジの構造を悪用した設計”って表現されとる。カーネマンのいうシステム1(直感思考)を狙い撃ちしてるんや。」
構造で見る:ナッジとダークパターンの違い
| 項目 | ナッジ | ダーク・コマーシャル・パターン |
|---|---|---|
| 目的 | 利用者の利益・社会的便益 | 事業者の利益・収益拡大 |
| 自由の実質性 | 保たれている(いつでも変更可) | 形式的にしか残らない |
| 心理効果の方向 | 行動を助ける | 行動を詰まらせる |
| 倫理的基準 | 透明性・可撤回性 | 不透明・誘導的 |
ダーク・コマーシャル・パターン=ナッジの構造を“利益の方向”にねじ曲げた設計。自由は形だけ、選択はコントロールされている。

「構造が同じでも、向けるベクトルが違うだけなんやな。」

「その通り。”自由を守りながら支える”のがホワイト。”自由を装って誘導する”のがブラック。結局”誰のための設計か”なんや。」
次章では、この“構造のズレ”が行政の世界では善意から生まれるケースを見ていきます。
リバタリアン・パターナリズムが掲げる「自由×理解×透明性」の設計哲学とともに、“詰まりをほどく”ためのナッジの再設計を考えていきましょう。
行政におけるスラッジとは?|“正義が詰まりすぎた”構造の問題
スラッジは「悪い人」が作るとは限りません。むしろ行政や公共サービスの現場では、“正しくしようとした結果”スラッジになっているケースが多いのです。
情報を「出す義務」と「使いやすさ」のジレンマ
行政の担当者は、
- 情報を網羅的に掲示する義務(透明性・公平性)
- 市民に理解してもらう責任(わかりやすさ)
──この2つの要請の間で、常に板挟みになっています。だからこそ、善意の構造がスラッジ化する。
たとえば:
- 申請ページに“全部”の要件を載せた結果、途中で離脱される
- フォームを丁寧に分けすぎて、画面遷移が多段化する
- 安全確認のためにチェックが多く、入力負担が大きい
いずれも「正しい」のに、「動けなくなる」。それが行政スラッジの典型構造です。

「行政サイトって、全部ちゃんと書いてあるのに、なんであんなに迷うんやろな。」

「そら”正義が詰まりすぎたスラッジ”や。悪気も悪意もない。ただ、情報を出さなアカン義務と、”分かりやすくしたい”気持ちが衝突してるんや。」

「なるほど。スラッジを意図せず生んでしまうってことか。”ちゃんとやろうとした人ほど詰まる構造”、なんか皮肉やな。」

「せやけど現場の人はみんな真面目や。”抜け漏れがあるとまずい”って構造的プレッシャーもある。だから、”悪気なしのスラッジ”が生じるんや。」
情報設計の再構築|リバタリアン・パターナリズムの視点で解く
リバタリアン・パターナリズムとは、「人の自由を守りながら、より良い選択を助ける」という考え方。行政がこれを取り入れるなら、「削る」ではなく「整理して残す」方向で設計することが大切です。
| 原則 | 行政での実践方法 | 目的 |
|---|---|---|
| 自由の確保 | 全情報は残す。ただし段階表示や折りたたみを活用。 | 透明性の維持 |
| 理解の支援 | 最初に“何をすればいいか”を図や一文で提示。 | 行動コストの削減 |
| 可撤回性 | 入力内容の修正・再確認を容易にする。 | 利用者の安心感 |
| 透明性 | 「行動科学の知見を活用しています」と明示。 | 信頼の確保 |
行政スラッジを“責めない目”で見る
行政サイトや手続きを“使いにくい”と感じたとき、多くの人は「なんでこんな不親切なんや」と思ってしまいます。でも実際には、担当者はみんな「ちゃんとした情報を届けよう」と努力している。スラッジは“怠慢”ではなく、構造的な副作用なんです。

「”減らす”じゃなく”整理して残す”って、ええ表現やな。」

「そう!ナッジの倫理は、”何を見せないか”やなくて、”どう見せるか”。利用者が迷わず動けるように設計するのが、リバタリアン・パターナリズムの本質や。」

「たしかに、”わざとやってる”って思ってたけど、よく考えたら”全部説明しなあかん立場”なんやもんな。」

「そうそう。”責任を果たすための構造”が、結果的に詰まりになる。でもその背景を知ると、”ああ、そういう事情やったんか”って思えるやろ。」

「構造を理解すると、イライラも減るんやな。」

「それが”構造的納得”や。怒りのナッジは、理解することやで。」
それでも「動きやすい社会」にするために
企業も行政も、そして私たち利用者も、みんな同じ構造の中に生きています。
- 正しさを追求するあまり、伝わりにくくなる行政。
- 利益を追求するあまり、誘導的になる企業。
- そして、理解より感情で反応してしまう私たち。
誰かが「悪い」わけではなく、構造のズレが行動を詰まらせているだけなんです。
参考文献・出典
- OECD (2024) Dark Commercial Patterns
- 環境省 日本版ナッジ・ユニット BEST (2024)『ナッジ×EBPM戦略』
- Richard H. Thaler (2018) “Nudge, not Sludge” Science

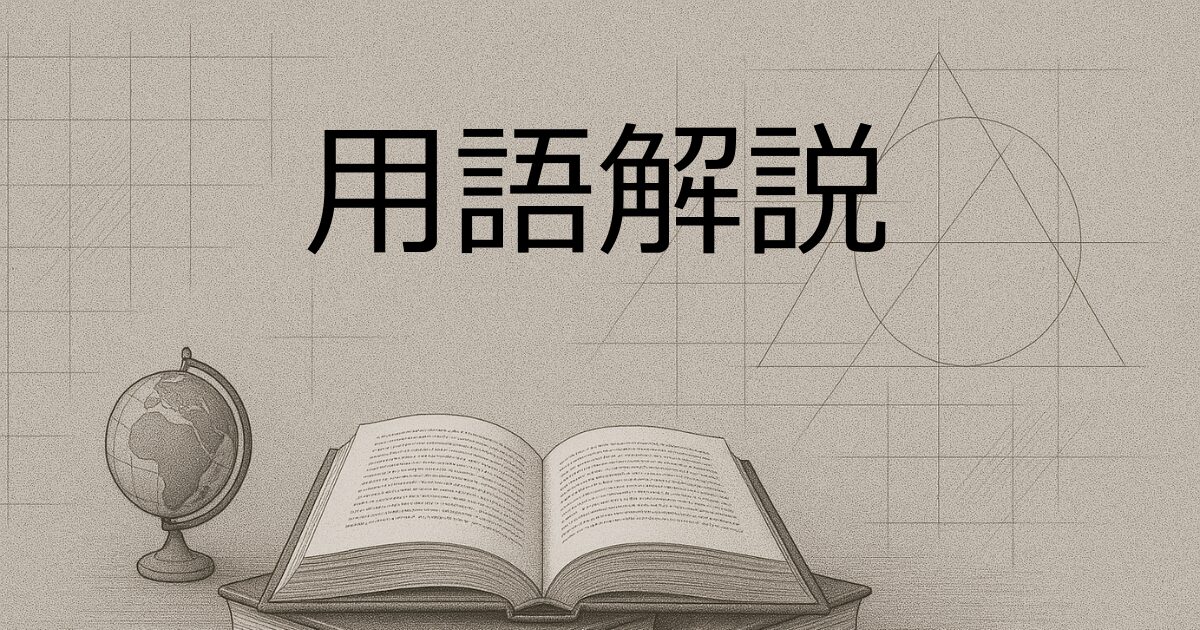
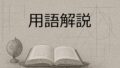
コメント