導入|割れ窓理論(Broken Windows Theory)とは
割れ窓理論は、1982年にウィルソンとケリングが提唱した社会理論です。小さな無秩序を放置すると、それが「秩序が守られていない」というシグナルとなり、より深刻な無秩序や犯罪を誘発するという考え方です。1990年代のニューヨーク市は地下鉄の落書き消去など「小さな犯罪」への対応を徹底し、重大犯罪も減少したことが有名ですが、あくまでこれは1つの結果の話。
本記事では1982年の提唱記事と、2008年のオランダで行われたフィールド実験を原典に基づき読み解いていきます。理論は効いたことがあるが、「正式な提唱内容を読んだことがない方」「実際に行われた実験までは知らない方」ぜひ最後までお付き合い下さい。
- 1982年の理論提唱と2008年の実証研究
- 6つのフィールド実験が明らかにした「無秩序の連鎖」のメカニズム
- 割れ窓理論の限界
原典① Wilson & Kelling(1982)|徒歩パトロールが示した秩序維持
1970年代半ば、ニュージャージー州が「Safe and Clean Neighborhoods Program」という治安対策を始めました。28都市で警官をパトカーから降ろし、徒歩パトロールに配置する内容です。知事や州当局は「犯罪が減るはずだ」と期待していました。しかし現場の警察署長たちは懐疑的でした。理由は以下の通りです。
警官たち自身も嫌がりました。
住民の安心感と記述的規範の作用
1980年、ワシントンDCのPolice Foundationが徒歩巡回の評価レポートを発表しました。
犯罪率:変化なし
「ほら見ろ、意味なかっただろう」──そう言いたくなる結果でした。でも、別の発見があったのです。

え、ちょっと待って。犯罪減ってないのに「安心した」って、それ住民だまされてるだけやないん?

そう見えるやろ?でもな、「安心感」って主観やけど、行動は変わってるんや。外出が増える、近所付き合いが戻る。それ自体が地域の秩序を支える力になる。だまされたんやない、「空気が変わった」んや。
住民はだまされた?いいえ。住民は徒歩巡回をしていた警官の活動をしっかりと見ていました。その具体的な活動を見ましょう。
ニューアークの路地で見えた「秩序維持」のリアル
研究者の一人、Kellingは実際にニューアーク市の徒歩パトロール警官に密着しています。
【ある路地の風景】
この路地を担当する警官──仮に「ケリー」とします──は何をしていたのか?
【ケリーのルール(住民と暗黙の合意)】
ケリーの行動は、その路地の「秩序」を維持することだったのです。地域の皆が了承している、「暗黙のルール」といった表現がいいかもしれません。そしてこのルールは、住民たちも理解し、支持していました。

これ法律のルールやなくて、ケリーが勝手に決めたルールってこと?それええんか?

ええとこ突くな。法律じゃなくて「地域の暗黙の合意」なんや。住民も商店主も「それでええ」と思ってるから成り立つ。逆に言えば、住民が支持してへんかったら、ただの権力の濫用になりかねん。
犯罪抑止ではなく「秩序維持」への注目
Wilson & Kellingはここで重要な区別しました。
犯罪抑止(crime prevention) ≠ 秩序維持(order maintenance)
多くの市民が恐れているのは、凶悪犯罪だけではないのです。物乞い、酔っ払い、騒ぐ若者、たむろする集団、娼婦、うろつく不審者──こうした「無秩序な人々」の存在そのものが不安の源であり、この「無秩序への恐怖」が地域を崩壊させる。人々は外出を控え、視線を合わせず、足早に立ち去るようになり、コミュニティの結びつきが弱まる。すると、犯罪者がつけ込んでくる。
「無秩序が無秩序を呼ぶ」Zimbardoの放置車実験
「無秩序が無秩序を呼ぶ」警官も社会心理学者も、この点では意見が一致しており、WilsonとKellingは、スタンフォード大学の心理学者Philip Zimbardoが1969年に行った実験を引用しています。
【方法】ナンバープレートを外し、ボンネットを開けた自動車を、2つの街に放置し、その後の変化を観察する。2つの都市で行った。
ブロンクス(ニューヨーク):
- 放置後10分:一家総出(父・母・幼い息子)が現れ、ラジエーターとバッテリーを持ち去る
- 24時間後:価値あるものはすべて略奪される
- その後:窓ガラスが割られ、シートが引き裂かれ、パーツがもぎ取られる
- 子どもたちが遊び場として使い始める
- 驚きの事実:これらの行動の多くは「よそ行きの服を着た、身なりの良い白人」が行った
パロアルト(カリフォルニア):
- 1週間以上:無傷のまま
- その後、Zimbardo自らハンマーで車の一部を破壊
- → すると、途端に通行人が破壊に加わり始める
- 数時間で車はひっくり返され、破壊された
- ここでも破壊者の多くは「まともな白人」だった

えっ、身なりの良い人がやるん?てっきり「もともとヤバい人」がやるもんやと思ってたわ。

それが一番大事なポイントや。「壊す人が悪い」んやなくて、「壊してもいい空気」が人を変えるんや。パロアルトなんか1週間無傷やったのに、ハンマーで一撃入れた途端に崩壊してるやろ。環境のシグナルが行動を引き出すんや。
「割れた窓」という比喩が示すメカニズム
長くなりましたが、やっと「割れ窓」が登場します。Wilson & Kellingは、有名な一節を書きました。
Social psychologists and police officers tend to agree that if a window in a building is broken and is left unrepaired, all the rest of the windows will soon be broken. This is as true in nice neighborhoods as in run-down ones. Window-breaking does not necessarily occur on a large scale because some areas are inhabited by determined window-breakers whereas others are populated by window-lovers; rather, one unrepaired broken window is a signal that no one cares, and so breaking more windows costs nothing. (It has always been fun.)
「社会心理学者も警官も、同じことを理解している。 建物の窓が1枚割れて、そのまま放置されると、やがてすべての窓が割られる。 これは高級住宅地でも貧困地域でも変わらない。 窓が割れるのは、その地域に『窓を割る人』が多いからではない。 むしろ、1枚の割れた窓が『誰も気にしていない』というシグナルになるからだ。 だから、もっと窓を割ることにコストがかからない。(それに、窓を割るのは昔から楽しい遊びだ。)」
この「割れた窓(Broken Windows)」という比喩が、後にこの理論全体の名前になるわけです。ケリーのような警官がやっていたのは、この連鎖の最初の段階を防ぐことだったのです。割れた窓を直すことはできない。でも、「誰かが気にしている」という空気を作ることはできる。犯罪率は変わらなかったかもしれない。でも、地域が崩壊する兆しを食い止めていたのです。
原典② Keizer(2008)実証|割れ窓理論は本当に起きるか
提唱はされたが実証はされていない
Wilson & Kellingの主張は大きな影響を与えました。1990年代、ニューヨーク市は地下鉄の落書き消しや無賃乗車の取り締まりを徹底し、犯罪率が劇的に下がった。「割れ窓理論の成功」と報じられたのです。多くの割れ窓理論の記事はこの成功例を記載しています。でも、批判もあった。
Wilson & Kellingの論文は説得力があるが、厳密な実証実験ではなかったのですね。
Science掲載のフィールド実験で何を確かめたのか
2008年12月、Science誌に一本の論文が掲載されました。
【著者】 Kees Keizer, Siegwart Lindenberg, Linda Steg(オランダ・フローニンゲン大学)
【タイトル】 The Spreading of Disorder
この論文は、オランダ・フローニンゲン市で行われた6つのフィールド実験の報告でした。フィールド実験(Field Experiment)とは、現実の環境で行われる実験のことです。実験室ではなく、実際の街中や公共の場で、人々の自然な行動を観察します。
Keizerらの研究では、6つのフィールド実験を通じて、実際の人々が無秩序のシグナル(落書き、違法駐輪など)にどう反応するかを観察しました。これにより、割れ窓理論が現実世界でも成り立つかを検証したのです。この実験の狙いは1つ
「ある規範違反が、別の種類の規範違反を誘発するか?」
落書きを見た人が、ポイ捨てをするか?ゴミが散乱した状況で、盗みを働くか?つまり無秩序は、種類を超えて伝染するのか?を確かめることでした。
注意:この実験の限界
ただし、内容に進む前に重要なヘッジを入れておきます。この実験は
- 2008年のオランダで行われた
- フローニンゲン市という特定の文化・社会背景
つまり
- 日本で同じ結果が出るとは限らない
- アメリカで同じ結果が出るとは限らない
- 2025年の現代で同じ結果が出るとは限らない
ただし、オランダは先進国であり、法治国家であり、教育水準も高い。そういう意味では、日本や他の先進国にとって参考になる環境だとは思います。Keizerらの実験は「代表的な一例」として、信頼性が高いから紹介する──そういう位置づけで読んでみて下さい。では、6つの実験を見ていきましょう。
実験1:落書きがあるとポイ捨てはどれだけ増える?
【設定】
自転車置き場において、自転車のハンドルに、白いチラシ(スポーツ用品店の広告)を輪ゴムでかける。路地にはゴミ箱なし。チラシを捨てるか、持ち帰るしかない。 自転車を取りに来た人がチラシのポイ捨てをカウント(他の自転車に掛けるはポイ捨てとカウント。)
【条件】
【対象者】各条件77人(合計154人)
【結果】
| 条件 | ポイ捨て率 |
|---|---|
| 秩序(壁きれい) | 33% |
| 無秩序(落書きあり) | 69% |
統計: χ²(1, 154) = 20.367, p < 0.001
落書きにより、ポイ捨ての頻度が有意に増加した。

33%→69%って倍以上やん。でもこれ、落書きがあると「この辺汚いし、もうええか」って気持ちになるだけちゃうん?単純な話やろ。

うん、それも含まれてる。でもな、注目すべきは「落書き禁止」の看板がちゃんとあるのに無視されてるところや。「ルールがある」と「ルールが守られている」は別問題ってことや。看板だけでは秩序は守れへん。
実験2:違法駐輪と「通り抜け禁止」違反の関係
【設定】
駐車場のメイン入口が臨時に封鎖され、「通り抜け禁止」の看板。封鎖しているフェンスに50cmの隙間がある。代替の入口は200m先と表示あり。フェンスに自転車を鍵で固定することを禁止する看板あり。駐車場に車を取りに来る人が、隙間から駐車場に入るかをカウント。
【条件】
【対象者】秩序44人、無秩序49人(合計93人)
【結果】
| 条件 | 通り抜け率 |
|---|---|
| 秩序(適切な駐輪) | 27% |
| 無秩序(違法駐輪あり) | 82% |
統計: χ²(1, 93) = 27.791, p < 0.001
フェンスに括られた自転車により、駐車場への入り方が有意に守られなくなった。
実験3:放置カートとポイ捨ての関係
【設定】
立体駐車場にて、車のワイパーに白いチラシ(実験1と同じ)を挟む。駐車場入口には「カートはご返却下さい」という目立つステッカー。車を取りに来た人がチラシをポイ捨てする人をカウント。
【条件】
【対象者】各条件60人(合計120人)
【結果】
| 条件 | ポイ捨て率 |
|---|---|
| 秩序(カートなし) | 30% |
| 無秩序(放置カートあり) | 58% |
統計: χ²(1, 120) = 9.766, p = 0.002
カートが散らかるとポイ捨て増える
実験4:花火の音とポイ捨ての関係
【設定】
駅近くの自転車置き場にて、自転車のハンドルにチラシ(実験1と同じ)。自転車を取りに来た人のチラシのポイ捨てをカウント。大晦日前2週間に実施。
【条件】
【対象者】秩序50人、無秩序46人(合計96人)
【結果】
| 条件 | ポイ捨て率 |
|---|---|
| 秩序(静か) | 52% |
| 無秩序(花火の音) | 80% |
統計: χ²(1, 96) = 8.587, p = 0.003
花火の音だけで、ポイ捨てが増えた。音だけでも影響を及ぼすことを示した。
実験5 & 6:落書きとゴミがもたらす窃盗実験(最も衝撃的な結果)
【設定】
郵便ポストに、白い封筒(中に5ユーロ紙幣が見える状態)を、ポストから半分はみ出させる。ポストの前を通った人の、封筒を盗む・開けるをカウント
【実験5:落書きあり/なし】
【実験6:ゴミあり/なし】
【対象者】
【結果:実験5(落書き有無)】
| 条件 | 窃盗率 |
|---|---|
| 秩序(きれい) | 13% |
| 無秩序(落書き) | 27% |
統計: χ²(1, 131) = 4.122, p = 0.035
【結果:実験6(ゴミ有無)】
| 条件 | 窃盗率 |
|---|---|
| 秩序(きれい) | 13% |
| 無秩序(ゴミ) | 25% |
統計: χ²(1, 143) = 3.545, p = 0.047
ポストの落書き、周囲のゴミ、いずれも窃盗を増やす

ポイ捨てまではわかる。でも落書きやゴミがあるだけで「金を盗む」まで行くか?さすがに飛躍しすぎやない?

俺も最初そう思った。でも数字は出てるんや。13%→25〜27%。これがこの論文の一番衝撃的なとこで、「汚い環境はポイ捨てを増やす」だけやなくて、「まったく別の種類の規範違反まで誘発する」ことを示した。次のセクションでそのメカニズムを説明するわ。
クロスノーム効果:異なる規範違反が伝染する仕組み
Keizerらは、これらの実験から割れ窓理論の核心的メカニズムを提唱しています。これが割れ窓理論の核心であり、この論文の最大の貢献です。
つまり、一つの規範違反が、全く別の種類の規範違反を誘発する。Keizerらはこれを「クロスノーム抑制効果(cross-norm inhibition effect)」と名づけています。
ある規範が破られているのを見ると、「適切に振る舞う」という全般的な動機が弱まる。すると、他の規範も守らなくていい気がしてくる。論文では、この背景にある心理メカニズムとして「goal-framing theory」も言及されています。人は「適切さの目標」「快楽の目標」「利得の目標」を持っており、無秩序を見ると「適切さの目標」が弱まり、他の目標が前に出る、という説明です。

なるほど…。ってことは、「ルールを守ろう」っていう気持ち自体が一個の塊で、どこか一箇所が崩れたら全体がグラつくってこと?

そうそう、まさにそれ。個別のルールが独立してるんやなくて、「ちゃんとしよう」っていう全体的なモードがある。そのモードが落書きやゴミで弱体化すると、ポイ捨ても窃盗も出てくる。これがクロスノーム効果の核心や。
Cialdini効果:「みんなやってる」がルールを上書きする
心理学者Robert Cialdiniの研究に基づく効果です。著者らは発見者のCialdiniの名前を取り、論文内でこう呼んでいます(影響力の武器を書いたあの「チャルディーニ」です)。人は「多くの人がやっている行動」を真似る傾向があり、「みんながやってるなら、正しいんだろう」という推論する効果です。少々学術的な言葉を出しますが、
この2つの規範のパワーバランスが崩れるのです。頭では「ダメ」とわかっていても、目の前の“みんなやってる”のほうが強い力を持ってしまう。落書きだらけの壁(記述的規範)は、「落書き禁止」の看板(命令的規範)を弱める。人は記述的規範に強く影響されるというわけです。
割れ窓理論の問題点と限界|ニューヨークの成功は本当にこの理論のおかげか?
割れ窓理論は影響力のある理論であることはここまでの提唱と実験で理解できますが、万能ではありません。ここからは理論の限界と批判を整理してきます。
ニューヨークでの「成功事例」が割れ窓理論だけでは説明できない理由
1990年代、ニューヨーク市は犯罪率が劇的に下がりました。ルドルフ・ジュリアーニ市長と警察本部長ウィリアム・ブラットンは、「割れ窓理論に基づく政策」を掲げました。以下のような対応を徹底したのです。
いわゆる軽微な犯罪の取り締まりです。ゼロ・トレランスと呼ばれます。その結果。犯罪率は確かに下がった。「割れ窓理論の成功例」として世界中に紹介されたのです。そしてこれが多くの割れ窓理論の記事が書く内容です。でも、本当に割れ窓理論のおかげなのか?
相関と因果の違い|短期実験と長期政策のギャップ
1990年代のニューヨークにおける犯罪減少は、割れ窓理論単独では説明しきれないと言われています。特にHarcourtとLudwigは2006年の論文で、「無秩序→犯罪」という単純な因果関係や、「軽犯罪の大量摘発=最適な犯罪抑止」という命題は支持されないと結論づけています。
【考えられる他の要因】
これらの要因が複雑に絡みあい、割れ窓理論だけで説明するのは無理があるのです。
限界:地域差・文化差と長期効果の未確定性
Keizerの実験は、因果関係を示したわけです。 「落書きがある → ポイ捨てが増える」 「ゴミがある → 窃盗が増える」しかしこれは
長期的な政策効果を示したわけではないのです。「地域の落書きを消し続けたら、5年後に犯罪率が下がるか?」これについては別の研究が必要となります。
ゼロトレランス政策と人種プロファイリングという副作用
そして割れ窓理論に基づく「ゼロトレランス政策」には、深刻な副作用もありました。代表的なものは差別的な取り締まりです。ニューヨークでは、軽犯罪の取り締まりがマイノリティに集中しました。これは「怪しい人物」として職務質問される対象が、黒人・ヒスパニック系に偏ったということ。果たしてこれは「秩序維持」なのか?それとも「人種プロファイリング」なのでしょうか?

うわ、これはキツいな…。理論自体は「環境を整えろ」って話やったのに、実際の政策では「人を取り締まれ」になってもうたんか。

せやねん。Wilson & Kellingの原典は「秩序維持」の話やったのに、政策に落とし込む段階で「軽犯罪の厳罰化」にすり替わった面がある。理論と政策の間にはいつもギャップがあるし、そのギャップで被害を受けるんは大体弱い立場の人なんや。ここは忘れたらあかんとこやな。
割れ窓理論は「万能の答え」ではなく「考えるフレーム」
ここまでを読むと、割れ窓理論の正しい理解が浮かび上がってきます。
同様に、日本への応用を考えるときも同じ注意が必要で
理論は「考えるための道具」であって、「答え」ではないのですね。
まとめ:理論は「考えるフレーム」—使いどころを見極める
- 割れ窓理論は1982年の観察から生まれた──警官の徒歩巡回が秩序維持をもたらすという発見
- 2008年に実証研究で確認された──一つの無秩序が別の無秩序を呼ぶ「クロスノーム効果」
- 万能理論ではない──犯罪減少は複数要因の結果であり、厳罰化には副作用もある
- 考えるためのフレームとして有用──「小さな乱れが大きな乱れを呼ぶ」という構造を理解する道具
1982年、ニュージャージー州から始まった。酔っ払いを座らせる。バス停での物乞いを止める。騒ぐ若者を静かにさせる。これは「犯罪抑止」ではなく、「秩序維持」をもたらしました。Wilson & Kellingは、この観察から「割れた窓」という比喩を生み出し、その効果はオランダで実証され「クロスノーム効果」が報告された。
一方で万能理論ではありません。ニューヨークの犯罪現象は複数の要因が重なった結果であり、ゼロ・トレランスは差別的な取り締まりという副作用も生んだのです。
小さな放置が連鎖を生む、という構造は経験的に共感でき、日常にも応用しやすい効果でしょう。ぜひこの考え方取り入れていきたいものです。
参考文献
- Wilson, J. Q., & Kelling, G. L. (1982). Broken windows: The police and neighborhood safety. The Atlantic Monthly, 249(3), 29-38.
- Keizer, K., Lindenberg, S., & Steg, L. (2008). The spreading of disorder. Science, 322(5908), 1681-1685.
- Harcourt, B. E., & Ludwig, J. (2006). Broken Windows: New Evidence from New York City and a Five-City Social Experiment. The University of Chicago Law Review, 73(1), 271–320.

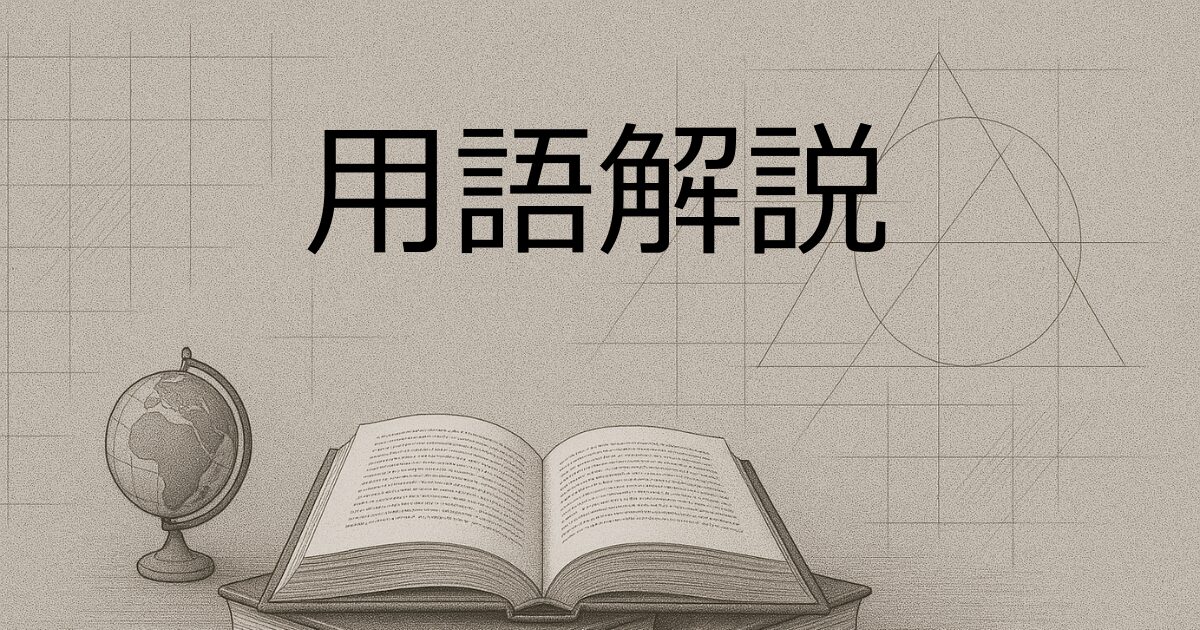


コメント