はじめに|不合理を笑わせる本、でもそれだけじゃない
ダン・アリエリー『予想どおりに不合理』は、行動経済学を一般に広めたベストセラーです。誰でも共感できる実験をユーモラスに語り、人間がいかに“不合理”かを見せてくれる。
ただしカーネマンで行動経済学に入った私からすると、正直アリエリーの語り口は軽いです。どの本を読んでも語り口がかなりフランクで、すぐアリエリーとわかってしまう。またそれか!と突っ込みたくなることもしばしばです。
どの味のカップラーメンを食べても“アリエリー味”がするような感覚。これはもちろんいい意味で言っていますよ。心のなかではリスペクトしている愛情表現。とはいえ、この軽さこそ日常に翻訳するにはちょうどいい。
今回は本書で印象的な実験を取り上げ、私自身の体験―保育園で草取り―と重ねながら書評してみます。
この記事でわかること
- ダン・アリエリー『予想どおりに不合理』の主要実験と理論
- 行動経済学が示す「不合理の中の合理性」
- 保育園の草取りで実感した社会規範の重要性
- サンデルの道徳哲学との意外な接点
火傷の包帯|「よかれと思って」がズレる瞬間
アリエリー自身が火傷患者として体験した「包帯のはがし方」。
本書の冒頭はこのやけどエピソードから入ります。冒頭から自分のきつい体験で始まり、一気に引き込まれるのがこの本の特徴です。
看護師は「痛みを短時間で済ませる方が優しい」と信じ、一気に包帯をはがす。 しかし患者のアリエリーは「多少長くてもいいから、最後を優しくしてほしい」と感じた。 ここに「専門家の合理性」と「当事者の合理性」のズレが潜んでいる。
このような意思決定のズレに興味を持ち、彼のそれからの研究の方針となったようです。
囮効果(デコイ効果)|比較の罠にハマる心理学実験
本書で最も有名な実験の一つが「囮効果(デコイ効果)」です。雑誌の購読プランを使った実験では、明らかに劣った選択肢(囮)を置くことで、人々の選択が変わることを証明しました。
- ウェブ版のみ:59ドル
- 印刷版のみ:125ドル(囮)
- ウェブ版+印刷版:125ドル
誰も選ばない「印刷版のみ」があることで、「ウェブ版+印刷版」がお得に見える。この囮を外すと、多くの人は安い「ウェブ版のみ」を選ぶのです。
私たちは絶対的な価値ではなく、相対的な比較で判断している。この「比較の罠」は、日常のあらゆる場面で私たちを不合理な選択に導いています。
ちなみに本書にはこれを合コンで使う裏技としても記述されています。詳細は私からは言えません。ちょっとブラック過ぎて(笑)気になる方はご自身の目でお確かめください。
イスラエル保育所の罰金──社会規範と市場規範のすれ違い
本書で有名になった事例があります。イスラエルの保育所で行われた「お迎え遅刻への罰金制度」の実験です。遅刻を減らす目的で罰金を導入したところ、逆に遅刻は増えました。罰金を課せば金銭的負担で遅刻が減るだろうと思っていたのに・・・。
理由は明快です。「遅刻して申し訳ない」という社会規範が、「お金で解決できる」という市場規範に切り替わってしまったからです。罰金を払えば堂々と遅刻できる──そう考える親が増えたのです。しかも制度を廃止しても遅刻は減りませんでした。いったん市場規範に切り替わった頭は、簡単には戻らないのですね。
ここで私が思い出したのはマイケル・サンデルの『それをお金で買いますか』です。サンデルは「市場が入り込んではならない領域がある」と道徳哲学から論じました。一方、アリエリーは実験から同じ真理に辿り着きます。アリエリーはフランクトークで笑わせながら、サンデルと同じ深い問いに到達しているのです。
この実験が示唆するのは、お金で解決できることと、お金で解決してはいけないことの境界線です。友情、愛情、信頼、責任──これらは市場で売買できません。しかし現代社会は、この境界線をどんどん曖昧にしていませんか?
保育園の草取り|社会規範ジレンマのリアル版
本を読んでいて思い出したのが、子どもの保育園での草取りでした。残暑残る中、保護者総出で校庭に集まり、炎天下で雑草を抜く。もちろん無償です。当日になると、必ず文句が飛び交う。
「なんで土曜の朝からやらなあかんねん」
「業者に頼めばいいやん」
「ボランティアやのに強制みたい」
それでも、誰も帰らない。結局みんな最後まで草を抜く。ここに働いているのは、まさに社会規範。
「子どものため」「周りがやってるから」「自分だけ抜けるわけにはいかない」という“不合理”が、人を動かしている。なんなら草刈り機を持ってきて刈ってくれる人もいる。もちろん燃料も自腹。
私も大変だなぁとは思いつつ、やはり使命感で草を取りに行きました。
もちろんフリーライダーは存在する。来ない人もいます。だから参加者の中には「不公平や!」と憤る人もいれば、「だったら金で解決せえや」と言う人もいる。しかし、市場規範に切り替えたらどうなるか。
「来ない人=悪者」ではなく「来ないのは自由」になり、翌年以降はさらに参加者が減る。人件費はかさみ、関係性は失われる。人件費や関係性のしわ寄せが来るのは?おそらく子どもと保護者では。
つまり、文句を言いながら無償でやる不合理な仕組みこそ、一番合理的なのではないでしょうか?
草取りの現場は、アリエリーが語る保育所の罰金制度のリアル版であり、社会規範ジレンマの生きた教材でした。
ヒューマンさんとエコノさんの感想戦|不合理との付き合い方

結局、不合理でええってこと?

ちゃうちゃう。不合理を理解した上で、うまく付き合えってことや。なんでも合理的にやりすぎたら信頼とか愛情とか人間味がなくなっていくんではないかって話や。

草取りも不合理やけど必要やもんな。業者に頼めば金もかかるし、案外その場でできるコミュニティとかがその後に役に立ったりするもんな

せや。市場規範だけじゃ世の中回らへん。社会規範も大事やねん。合理的思考だけで暮らしてみ?冷たい世の中になるで。

たしかにそうやな。アリエリーの本、軽いけど深いな

多分あの軽さは計算やで。難しい話を笑いながら理解させる戦略やと思うで?

火傷の話は重いけどな。でもあの話で一気に引き込まれるんや。

あの体験があるからこそ説得力があるんや。つらい体験から生まれた研究方針やから、発言に重みあるよな。
総評|「予想どおりに不合理」の二重の意味
『予想どおりに不合理』を読むと、人間が合理的に考えるはずなのに不合理に転ぶ、という実験が山ほど出てきます。だが本当に面白いのは、そこで終わらないことでしょう。
草取りの例に見たように、不合理に見える仕組みのほうが、長期的には一番合理的という逆説が浮かび上がる。この不合理は、実は人間社会を円滑に機能させる潤滑油であったりする。
つまり「予想どおりに不合理」というタイトルは、こうも読めると思うのです。
人間は不合理に振る舞う。だが、その不合理の中にこそ、人間らしい合理がある。
この二重の意味に気づいたとき、本書は単なる実験ネタ集を超えて、私たちの日常を考えるレンズになる。そして本を閉じたあとに待っているのは、さらに“予想以上に不合理”な子どもたち。
「最後の一回!」が十回続く帰宅交渉や、水たまりに全力で飛び込む瞬間…。
アリエリーの実験以上に、日常には予想外の不合理があふれている。
だから私は、この本をきっかけに「予想以上に不合理」シリーズとして子育てのリアルを掘り下げています。
アリエリーの軽さには違和感を覚えることもありますが、フランクトークで笑わせながらサンデル級の本質にたどり着く力は確かだと思っています。といいますかこのフランクトーク、私はアリエリーが「行動経済学を日常に」を狙ってやっているスタイルだと勝手に考えています。
不合理を抱えることが合理になる。
この逆説を笑いながら体感できる一冊として、『予想どおりに不合理』は今も読み返す価値があるでしょう。

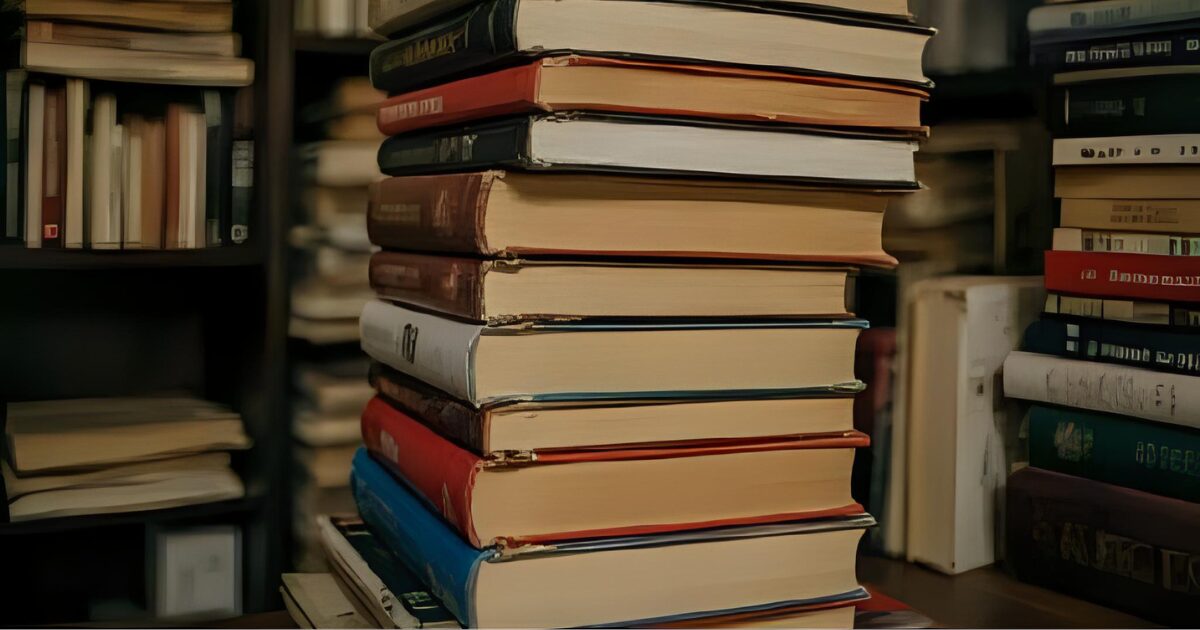
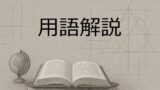
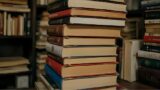


コメント