コンプロミス効果とは|中間を選びたくなる心理
コンプロミス効果(Compromise Effect)とは、消費者行動において、複数の選択肢の中から中間的な選択肢が選ばれやすくなる心理的傾向のことです。
例えば、3つの選択肢A(低価格・低品質)、B(中価格・中品質)、C(高価格・高品質)があった場合、多くの人はBを選びます。これは極端な選択肢を避け、「中庸」を選ぶ人間の心理的傾向によるものです。
コンプロミス効果の心理メカニズム
- 極端な選択を避ける心理:最も安いものは品質に不安があり、最も高いものは「必要以上に払いたくない」という心理が働く
- 正当化しやすさ:中間の選択肢は「コスパが良い」と自分自身や他者に説明しやすい
- 損失回避:最も安いものを選ぶと品質面での損失、最も高いものを選ぶと金銭面での損失を恐れる
- 社会的な評価への不安:「ケチ」とも「見栄っ張り」とも思われたくない
- 認知的な負担軽減:複雑な比較検討を避けて「無難な選択」で済ませる
- 後悔の最小化:極端な選択による失敗リスクを避ける心理
コンプロミス効果のマーケティング活用事例
この効果を理解した企業は、意図的に「売りたい商品」を中間に配置するという戦略を取ることがあります。高額な選択肢を置くことで、中間の商品の価値が相対的に高く感じられるようにするのです。
日常生活での具体例
- レストランメニュー:最も高い料理があることで、中価格帯の料理が「お得」に感じられる
- サブスクリプション:スタンダード・プレミアム・エクゼクティブの3プランがあると、プレミアムが選ばれやすい
- 家電製品:エントリーモデル・標準モデル・ハイエンドモデルの構成で、標準モデルが売れる
米田語で解説!松竹梅とコンプロミス効果
「松竹梅だと竹を選ぶ!」という人間心理
さて、ここからは教科書的な内容を米田の言葉で解説していこう。
学術用語より生活感プンプンでいくで。日本人が一発で理解する表現を提示しよう
「松竹梅だと竹を選ぶ!」
これでどうだ!まぁ多くの解説記事が同じ文言を使っているのですが。
そこから様々な変法が生み出され、世の中に満ち溢れているので米田の経験を交えつつ解説していこう。
家電量販店での実体験
先日、ドライヤーが壊れて家電量販店にお邪魔した。
とあるメーカーのちょっといいドライヤーを選ぼうとしたところ、明らかな松竹梅構成。
で、松を見てみたら機能的にはほとんど価値見い出せなかったのよ。スイッチが無駄スタイリッシュで液晶までついて、挙げ句多彩なモードとてんこ盛り。で価格数万円プラス。超高機能を求めるユーザーはメーカーも少数だと認識しているだろうから、おそらく竹を売るためのマーケティング戦略と私は確信した。だって梅でも結構いいレビューが書かれていたからね。最高品質はいらないけど、一番最低ランクはなんかヤダ。うまい人間心理を突いてくると感心してしまうよね。
損失回避が働くと「竹」が選ばれやすい理由
実際のところ、日本の家電メーカーの技術力はすごい。梅でも生活に支障ないことが多いし、竹でさえ使い切れない機能がゴロゴロある。
皆さんも思い出してみて?
ドライヤーでもテレビでも、使ったことのないボタンやモード、あるでしょ?
誰がこのボタン使ってんの?的なやつ。
だからこそ、買い物するときはまず自分のニーズを確認して、必要最小限を選べばOK。ここでも損失回避が働いてるんだと思う。「もし梅を選んで後で欲しい機能がなかったらどうしよう」って不安。でも、その不安だけで高いモデルに飛びつくのは典型的な心理の罠。不安だからって高いの買うんじゃない(笑)
ただし、梅モデルで重要な機能を意図的に除外していることもあるから注意。これも竹に誘導するビジネスモデルだからね。こう見ると家電とかの比較表、馬鹿にできんでしょ?
コンプロミス効果を回避する3つの質問
- 一番下のモデルに本当に不足があるか?
- 真ん中と下の「差額分の機能」を使うか?
- 「みんな選んでる」以外の理由があるか?
この3つに答えられないなら、それはコンプロミス効果かも。
米田語のまとめ
私の経験からを例を挙げてみたけれども、この視点をもって世の中を俯瞰してみると、恐ろしいほどこの効果が蔓延していることに気づくと思う。
ちょっと次に何か買い物での選択で迷ったら、コンプロミス効果を思い出してみて。「あ、米田のところで見たやつやん」って呟いたらこの記事の優勝!(笑)
更に、一定数超高機能の家電やサービスが必要になる人もいるからね。そういった人にとっては松は重要。松を作るというのは会社の技術力をアピールするのと同時に、竹を売りやすくするという一石二鳥の効果があるわけだ。
ま、私も趣味のカメラとかはコンプロミス関係なく松直行だけどね笑
ヒューマンさん×エコノさん劇場
店頭にて
ヒューマンさん(人間代表):何やねん。松モデルごっつい高いやん。俺には分相応やな。1個下の竹モデルにしとこ。これなら恥ずかしくもないやろ。店員さんも一番の人気モデル言うてるし。
エコノさん(合理的経済人):まてまて。中間でも案外分相応やもしれんで。機能の比較表やるけ、にらめっこしときー。
ヒューマンさん(人間代表):いやいや、一番安いのはなんか不安やねん。
帰宅後
ヒューマンさん(人間代表):竹モデル買ってきたでー
エコノさん(合理的経済人):で、梅モデルとの差の機能、使うんか?
ヒューマンさん(人間代表):・・・・
エコノさん(合理的経済人):お手本みたいにコンプロミス効果にハマっとるで
ヒューマンさん(人間代表):うるさいわ!みんなこれ選んでたんや!!
まとめ|真ん中病から卒業しよう
松竹梅があったら反射的に竹を選ぶ。これ、人間に普遍的に存在する現象だけれど、日本語で表現するのであれば「出る杭は打たれる」という感じかな。目立たず、でも恥ずかしくもない、ちょうどいい真ん中という安全地帯。 これは人間の「失敗・後悔したくない」「自分・他人に正当化しやすい」が生み出す思考のショートカット。
でも知ってしまった今、あなたはもう違う。次に松竹梅を見たら、まず梅の実力を確認してみて。 案外それで十分かもしれませんよ。
もちろん、吟味した結果の竹ならそれはそれでOK。大事なのは「なんとなく真ん中」からの卒業です。
ヒューマンさんみたいに「みんなが選んでるから」じゃなくて、エコノさんみたいに「機能表とにらめっこ」してから決める。 それがコンプロミス効果に負けない買い物術です。

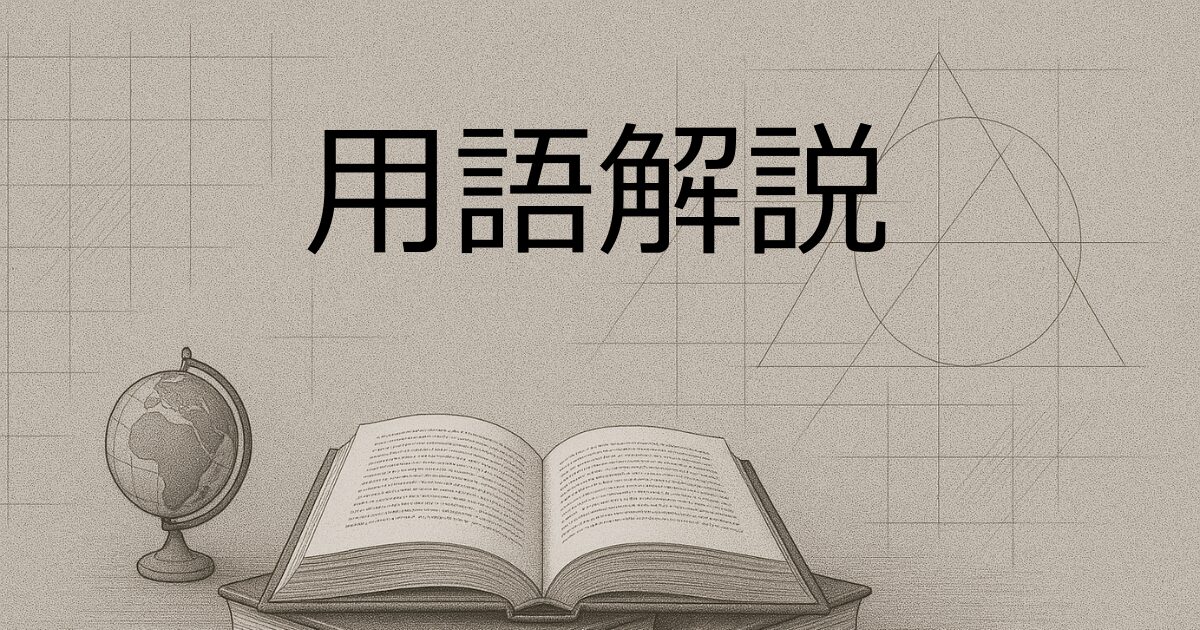

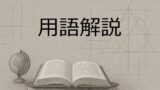
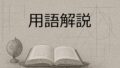
コメント