導入|フルエアロのミニバンから降りてくるパパママ現象
保育園の送迎のときに見かける車があります。車高短フルエアロのミニバン。スモーク越しにチラッと見える、後部座席のチャイルドシート。ハンドルカバーはギラギラ。
スライドドアが開いて──
出てきたのは、どう見ても“昔はちょっと悪いことしてたぜ”的なパパ。
──正直、構えるよね。
「おおっと、こっち見んなよ…」って、つい身構えてまう。でも見た目で対応を変えるなんて失礼、こちらから挨拶すると、礼儀正しく丁寧な挨拶が返ってくる。
……あれ? 脳が一瞬フリーズする。ちょっと突っ込んで世間話してみると、言葉遣いはすごく丁寧、子煩悩感すごく出てる、先生への対応もこれでもかと腰が低い。
たったの車と見た目で、「少し怖い人」って判断していた自分が恥ずかしくなってくる。実際は全然違う。
これがまさに、代表性ヒューリスティック(representativeness heuristic)。
人は「見た目や雰囲気が、ある典型的なイメージにどれくらい似てるか」で、その人の中身や確率まで勝手に決めつけてしまうんです。
- 代表性ヒューリスティックの正確な定義と提唱者
- なぜ人は“それっぽさ”で判断してしまうのか
- 「リンダ問題」「トムW問題」が示す心理の罠
- この知識を知ることで判断の質がどう変わるか
難しく聞こえるけど、要は「見た目とか雰囲気で“たぶんこうやろ”って決めつけてまう」って話です。
理論定義|代表性ヒューリスティックの意味と背景
代表性ヒューリスティック(representativeness heuristic)とは、1974年に心理学者のエイモス・トヴェルスキー(Amos Tversky)とダニエル・カーネマン(Daniel Kahneman)が提唱した認知バイアスの一種です。
正式な定義は以下の通り。
「ある対象や出来事が、典型的なカテゴリーの特徴にどれだけ似ているかによって、その確率や頻度を判断してしまう心理的傾向」
たとえば、「真面目そうな見た目の人=几帳面」「やんちゃっぽい見た目の人=怖そう」といったように、“似ている”という印象だけで確率を飛び越えてしまう。日本人が好きな「A型=几帳面」も該当します。
この「印象による確率のすり替え」が、のちの「リンダ問題」や「トムW問題」で実証的に示されました。
脳の2つのシステム
カーネマンは著書『ファスト&スロー』で、人間の思考を2つに分けました:
システム1(直感的思考)
- 自動的・高速・無意識
- 「車高短フルエアロ=やんちゃ」と瞬時に判断
- エネルギー消費が少ない
システム2(熟慮的思考)
- 意識的・低速・論理的
- 「待てよ、見た目で判断は良くない」と考え直す
- エネルギーを大量消費
代表性ヒューリスティックはシステム1の暴走。 だから意識的にシステム2を起動させる必要があるんです。
リンダ問題|“それっぽい物語”の罠
行動経済学の書籍に必ず登場するのが、リンダ問題(Linda Problem)。トヴェルスキーとカーネマンが1970年代に行った、有名な実験です。
リンダは31歳、独身。外交的で聡明。大学では哲学を専攻し、差別や社会正義の問題に強い関心を持っていました。反核運動に参加したこともあります。さて、次のうちどちらがよりありそうでしょう?
A:リンダは銀行員である。
B:リンダは銀行員でフェミニスト活動にも関わっている。
──あなたなら、どっちを選びますか?
実験では多くの人がBを選びました。「社会正義の問題に関心がある」「哲学専攻」などの情報が、“フェミニスト”という言葉とストーリー的にハマるからです。けれど、確率で考えると、
- 「銀行員かつフェミニスト」(A∩B)より
- 「銀行員」(A)のほうが多いのは当たり前。
どちらも“銀行員”ではあるけど、Bは条件が増えてる分だけ確率は下がる。
実はカーネマンたちが行った実験結果は衝撃的でした。なんと大学生の約85〜90%がBを選択というのです(出典:ファスト&スロー,2012年,早川書房)
つまり、「それっぽい」物語のほうを選んでしまうことで、私たちは知らずに確率を無視するんです。
この問題は今から50年前の実験で、かつ海外の実験では日本の文化とは比較しにくい。ということで冒頭の私の恥ずかしいエピソードのパパさん、以下の選択肢のうちどちらの確率のほうが高いでしょう。
A:一般企業で営業職の会社員
B:一般企業で営業職の、昔ちょっとやんちゃしてた会社員
Bを選びたくなりませんか? なぜなら、車高短・フルエアロ・ミニバンといった“断片情報”から、脳が勝手に「ちょっとやんちゃ」な人物像を補完してしまうからです。
リンダ問題を経験した方はもう騙されませんね。確率的には、ただの「会社員」のほうが圧倒的に多い。

いやいや、フルエアロ車高短とか、もう”ちょっとやんちゃ”一択やろ。(笑)

せやけど、「やんちゃ」って条件が増えた時点で確率は下がるんやで。
学校で習ったベン図、思い出してみ? A∩B は A に含まれるから、範囲は必ず狭なるやろ?

あー…ワイの脳、見た目とストーリーの整合性で選んどったわ。

そう。”それっぽさ”ってやつが、確率を上書きしてまうんや。
でもその瞬間を笑えるようになったら、もう上級者やで。
トム・W問題|印象が未来を歪める
「トム・W問題」は、代表性ヒューリスティックが“未来予測”でどう悪さするかを示す定番の課題です。こちらもカーネマンとトヴェルスキーが行った実験。肝は、印象の一致度が高いほど、現実の確率(母集団の比率)を無視してしまう点にあります。
トム・Wは大学院生。知能が高いが、真の創造性には欠けている。
彼は秩序と明確さを求め、あらゆる細部が適切な場所に収まるような整然としたシステムを好む。
彼の文章はやや退屈で機械的だが、ときおり少しダサいダジャレやSF的な想像力の閃きによって彩られることがある。
彼は有能であろうとする強い欲求を持つ一方で、他者への共感や親しみには乏しく、人付き合いを楽しむタイプではない。
自己中心的ではあるが、同時に深い道徳心を持っている
彼の特徴が下記の分野の典型的な大学院生にどのくらい似ているか考え、似ていると思う順に番号を振ってください。
経営 ・コンピュータサイエンス ・工学 ・教育学 ・法律 ・医学 ・図書館学 ・物理学・生物学・社会学
この実験では多くの人が「コンピュータサイエンス」を1番に選んだそうです。トムのプロフィールにおける印象と強く一致するからです。ここで外してはいけないのが、母集団の大きさ(ベースレート)
- 1970年代当時、コンピュータサイエンスよりも圧倒的に経営や教育学のほうが学生数が多いと考えることができきる。
- 母集団が大きいほど、そこから無作為に1人を取ったときに該当する確率は上がる。
──つまり、トムW問題が教えてくれるのは、「印象の物語」より「母集団」という事実を考えることが正しい、ということ。
日本版トムW問題(ベースレートを意識して解く)
1970年代のアメリカの専攻の母数ではわかりにくいので、日本に落とし込みましょう。
トモヤくんは昔から生き物が大好きで、理科の実験が大好きでした。
学校では学年でトップクラスの優秀な成績で、特に理系の科目が抜群に得意でした。
社会貢献への意欲が極めて高く、困っている人を放おっておけない優しい人です。
さて、どちらがよりありそうでしょう?
A:トモヤくんは製造業関連職
B:トモヤくんは医師
直観はBに流れますが、現実の母集団を見るとまったく違います。
現実の数字を見てみよう
- 医師数:約34万人(全人口の約0.3%)
出典:厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計(2022)」 - 製造業就業者:約1,000万人(全人口の約8%)
出典:総務省「令和4年就業構造基本調査の結果」
つまり、製造業で働く人は医師の約30倍近くも多い。
印象はB(医師)に一致しても、確率はA(製造業)のほうが圧倒的に高いのです。
これがまさに、「ベースレート無視(base-rate neglect)」の典型です。

いや、これはどう見ても”医師っぽい”やろ。生物が好きで理系、成績トップクラス、社会貢献欲まであるって。完全に一致やん?

一致してるのは”印象”や。確率は母集団で決まる。製造業と医師の母数、考えてみ?

なるほど…印象で先に答えを決めて、数字を後付けしてたんやな。

せやで。印象は気持ちええ。でも確率は気持ちとは別もんや。まずベースレート(母集団)を見よか。
製造業は日本の人口の約8%を占める巨大セクター。一方、医師は全人口の0.3%ほど。
つまり、「理系で頭がいい=医師になっている確率」は、私たちの直感よりはるかに低い。
この“直感のずれ”こそが、代表性ヒューリスティックの本質です。
まとめ|“らしさ”が真実を上書きする構造
1️⃣ リンダ問題:物語の“それっぽさ”が、確率の法則を上書きしてしまう。
2️⃣ トムW問題:「理系っぽい」「医師っぽい」などの一致感が、母集団という事実を無視させる。
3️⃣ 日常生活:フルエアロのパパ、A型の几帳面説…印象は便利だが、正確さとは別もの。
4️⃣ 対処法:一拍おいて“確率”を思い出す。
「これは私の代表性ヒューリスティックかも」と気づければ、もう思考の上級者。
私たちはいつも、“見た目や雰囲気で確率を無視する生き物”。けど、そこに気づけた瞬間から世界は少し違って見える。次に車高短フルエアロのミニバンから降りてきたパパママを見たとき、心の中でそっと言おう。
「これは私の代表性ヒューリスティックが話してるだけやな」
──そう思えたら、もうあなたは“見た目に支配されない人”です。

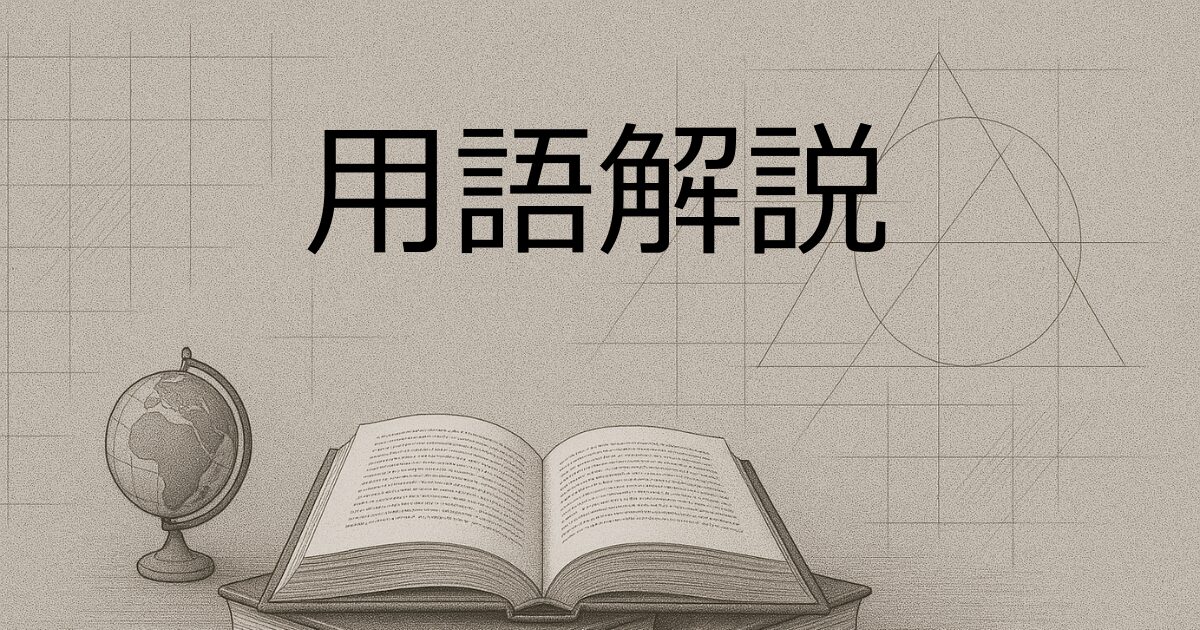
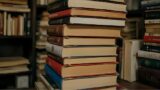
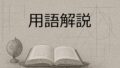
コメント