導入|遠くて予約も取れないのに、なぜ美容室を変えられないのか
私、何年も同じ美容室に通っていました。正直、家から遠いし、予約もなかなか取れない。 しかも、仕上がりが“最高!”ってほど気に入っているわけでもない。
それでも、なんとなく通い続けてしまう。近所に歩いて行ける店もあるのに、「今回はやめとこ」と先延ばし。
唐突に行かなくなるのも悪い気がするんですよね。長くお世話になってるし、なんか裏切るみたいで。それに、新しい店に行って仕上がりがイマイチだったらどうしよう──そんな不安も頭をよぎる。
でもある日、思い切って別の店に行ってみたんです。結果、完璧な仕上がり。 「なんで今まで変えへんかったんやろ」と思いました。
そう、これがまさに現状維持バイアス(Status Quo Bias)。人は「変える」より「今のまま」を好むようにできているんです。
この記事でわかること
- 現状維持バイアスの意味と正体──なぜ人は「変えたほうが得」とわかっていても動けないのか
- 脳の構造から見る”変えられない”理由──現状を参照点にして、損失を過大評価してしまう仕組み
- なぜ「後悔したくない」と思うほど動けなくなるのか──損失回避に加え、責任や後悔を避ける心理の存在
- 身近な現場で現状維持はどう顔を出す?──美容室・職場・買い物・人間関係など、生活のあらゆる場面
- どうすればこのバイアスと上手に付き合えるのか──”戦う”のではなく、”参照点をずらす”ための設計思考
理論定義|現状維持バイアスとは何か
現状維持バイアス(Status Quo Bias)とは、
人が合理的な理由がなくても「今の状態をそのまま続けよう」とする傾向のことです。
この概念を最初に明確に示したのは、経済学者のウィリアム・サミュエルソンとリチャード・ゼックハウザー(1988)でした。彼らの実験を簡単に次項で見ていきましょう。
「現状維持」というラベルの魔力を証明した実験
486名の学生に、投資や転職などの意思決定シナリオを提示し、選択をしてもらいました。
ここでの工夫は、全く同じ選択肢を2つの異なる見せ方で提示したことです。
パターンA:「以下の選択肢から選んでください」と全てを対等に提示
パターンB:一つを「現在の状態」として提示
一例を挙げましょう。以下の通りです。
あなたは遺産を相続しました。投資を検討しています。
パターンA:「①〜④の4つのプランのどの方針としますか?」
パターンB:「遺産の大部分は①プランで投資中でした。①〜④のどの方針としますか?」
このような形で提示しました。
結果は明快。「現状」とラベルされた選択肢は、中立的に提示された時より平均17.7%も多く選ばれたのです。
この実験は、私たちが「今のまま」を選ぶ傾向が、合理的な理由ではなく純粋に心理的なバイアスであることを証明しました。変化を避ける私たちの性質は、思った以上に強固なのです。
この心理の背景には、カーネマンとトヴェルスキー(1979)のプロスペクト理論があります。
人は利益と損失を「絶対値」ではなく、いま置かれている状態(参照点/reference point)からの変化として感じ取ります。そして、損失は同じ大きさの利益よりも強く痛みを感じる(損失回避/loss aversion)のです。
この二つ──参照点依存性と損失回避が組み合わさることで、「現状を変える=損をするかもしれない」という感情が生まれます。
さらに、後悔したくない心理の後悔回避(regret aversion)やめんどくさいと感じる認知的慣性(decision inertia)が拍車をかけます。
つまり現状維持バイアスとは、現状を”心理的な基準点”とし、そこからの変化を過大にリスクとして感じる人間の反応なのです。
- 損失回避(Loss Aversion):損失の痛みは、同じ大きさの利益の約2倍強く感じられる
- 参照点依存性(Reference Dependence):現状が基準点となり、そこからの変化を「損」として知覚する
- 後悔回避(Regret Aversion):「変えて失敗したら…」という想像上の後悔を避けようとする
- 認知的慣性(Decision Inertia):選択を変えるにはエネルギーが要るため、思考の惰性が働く
フランク解説|なぜ人は「今のまま」が安心に感じるのか
上記の理論を携えて、冒頭の美容室エピソードの時の頭の中を覗いてみましょう。頭では「こっちのほうが仕上がりがいいかも」「家から近い」とわかっているのに、なぜか心が動かない。
「もし仕上がりがイマイチだったらどうしよう」
「今の美容師さんに悪い気がする」
「変えて後悔したらイヤだな」
─これがまさに、現状維持バイアスが働いている瞬間です。
人の脳は、新しい行動=損をするかもしれない変化と感じやすい構造になっています。現状を参照点として、そこからの変化を「利益」か「損失」として評価する。
そのとき、損失は同じ大きさの利益よりもずっと強く心に響く。つまり、変化にはリターンがあっても、脳の中では「仕上がりが悪い」「美容師さんへの罪悪感」が本来の値よりも過剰に声がデカくなっているわけです。
さらに変えるという行為には、”自分の判断で髪型が失敗するかもしれない”という責任が伴います。このとき生まれるのが、後悔回避。「今のままにしておけばよかった」と感じる未来を避けるために、人は無意識に”決断しない”という選択を取ることがあります。
そしてさらに認知的慣性。変えるには情報を集めて考え直すエネルギーが要る。その手間を省くために、私たちは「今のまま」を選びやすくなるのです。
現状維持バイアスとは、損失の痛み・後悔の予防・思考の省エネが重なって”安心という錯覚”をつくり出す心理的な安全装置なのです。

なるほど!つまり変化のうちプラス値よりもマイナス値を脳がデカく見積もるバグやな?

そうそう。だから理性では「変えたほうが得」ってわかってても、感情が「いや、今のままがええやん」って引き止めるんやで。

挙げ句、変えるには手間も後悔もつきまとうから、わざわざやらへんってことやんな。

せやせや。わざわざ手間かけてなんかあったら嫌やし、と脳がビビっとるねん。でな、実は客観的に見たら、手間なんかたいしたことないことが多いねん。
進化論で読み解く|変化を避けるのは脳の安全装置
現状維持バイアスを「バグ」と捉えがちですが、進化の観点から見れば、これは数十万年かけて磨かれた生存戦略という仮説を立てることができます。
私たちの祖先が狩猟採集をしていた頃、「昨日と同じ」は「昨日も生き延びた」という実績の証。未知の果実、新しい狩場、見知らぬ部族との接触──これらはすべて、命に関わるリスクだった可能性があります。
「新しいもの=潜在的な脅威」という方程式が、生き残りの鍵だったのです。冒険しすぎた場合の例を考えてみましょう。
- 毒のある植物を食べる → 死
- 危険な地域に踏み込む → 捕食者に遭遇
- 敵対的な部族と接触 → 命の危機

人間の「変わりたくない」って気持ち、実はけっこう昔からの”クセ”やねん。

え、昔ってどれくらい昔?

狩猟採集の時代までさかのぼるんや。当時は、知らん食べ物を試したり、見慣れん土地に踏み出したりすることが命に関わるリスクやった。「昨日と同じ行動を続ける=今日も生き延びられる」っていう成功体験の積み重ねが、安全のサインやったんや。

なるほど。つまり、”変化=危険”が脳に染みついてるってことか。

そういうこと。まぁ仮説の一つでしかないけどな。「慎重すぎてチャンスを逃す」よりも、「油断して命を落とす」ほうが致命的。だから、脳は自然と”慎重寄り”にチューニングされてるんや。
日常での現状維持バイアス|あらゆる場面で作動している
| カテゴリ | 具体的な状況 | 行動・心理の例 | 背景にある心理構造 |
|---|---|---|---|
| ① 仕事の現場 | 新システム導入後も旧式を使い続ける | 慣れてるからこのままで | 習慣化された安心感が参照点を固定 |
| チーム編成が変わっても前例にこだわる | 前の上司の方がやりやすかった | 参照点依存 | |
| ② 消費行動 | サブスクを解約できない | また使うかもで放置 | 損失回避(使えなくなる痛み) |
| 外食でいつものメニューから変えられない | 失敗したら嫌やし | 経験の慣性+リスク回避 | |
| 携帯プランを見直さない | 手続きが面倒 | 認知的慣性(考える負担を避ける) | |
| ③ 人間関係 | 合わないグループを抜けられない | 悪い人じゃないし | 後悔回避+社会的コスト意識 |
| パートナー関係に不満があっても続ける | 一からやり直すのはしんどい | 損失回避(別れを損失として知覚) |

こうして見ると、変わらない理由って”性格”やなくて、脳の仕組みっぽいな。

そうそう。怠けてるんやなくて、リスクを避けようとする心の省エネ設計なんや。大事なのは、「どこでその省エネを解除するか」ってとこやね。
現状維持バイアスとの付き合い方|”変化の設計”で動けるようにする
現状維持バイアスは「悪いクセ」ではなく、脳の省エネ機能。だからこそ、無理に逆らうより、設計を変えたり、そもそもクセを利用したほうがうまくいきます。
① デフォルトを逆手に取る
典型的な現状維持バイアスの有効利用です。人は「何もしない」を選びがち。ならば、”何もしなくても望ましい行動になる”ように設定してしまえばいい。
自動積立投資や自動貯金で、「何もしない=貯まる」設計にするといったものが典型です。
② 損失と利益を客観視する
人の脳は「損するかも」の声がデカくなる。ではそれぞれを書き出してまっさらな頭で客観視してみましょう。ケータイキャリア変更を例で考えます。考えうる損失は
- キャリアメールが使えなくなる
- 電波状況が悪くなる
- 長期契約で割引されている
- 契約手続きが面倒
では利得は
- 月々5,000円安くなる
- 選ぶ回線により電波状況がよくなる可能性も
いいですか?今あなたの中で損失が客観的値より重みが増している可能性があります。フラットで見ましょう。
- キャリアメール使ってます?なくて困ることありますか?本当に困るなら月5,000円で代替できませんか?
- 電波状況、周りで格安SIM使っている人で、困っている人います?逆に他の回線で良くなるかもしれませんよ?
- 長期契約割引、月5,000円を上回る割引なんですか?
- 契約手続き、1時間もあれば終わりません?1時間で月5,000円ですよ。時給換算してみて下さい。
ほら、「私、損失値バグってた」と思いませんか?
客観視するだけで「変更してみるか」と思ったのではないでしょうか。
③ 小さな実験から始める
大きく変えようとすると、脳が抵抗する。だからまずは安全なテストから始めましょう。
- 新しい美容室。「前髪カットだけ、少し整えるだけ」などリカバリできる範囲で行ってみる。
- 新しい仕事手順。まずは自分だけで始めてみる。うまく行ったら係→課→部と広げてみる。
- サブスク解約。利用頻度が低いものからやってみる。何も変化がなければOK、損失だと思ったら再契約すれば良い。リカバリ容易。
変化のコストを最小化すれば、損失回避も最小化。その成功体験が”新しい参照点”になり、やがて現状維持バイアスの向きを逆転させられる。

なるほどな。”根性で変わる”んやなくて、”仕組みで変える”んやな。

せやね。人間の脳は気合では勝てへんけど、設計には負ける。行動経済学の本質は、意志よりも環境デザインやで。
まとめ|現状維持バイアスは敵じゃなく”扱い方”の問題
- 本質:現状を参照点にして、そこからの変化を”損”として過大に感じる心理。
- 主要メカニズム:損失回避 × 参照点依存(+ 後悔回避・認知的慣性)。
- 現代での誤作動:昔の「変化=危険」が、今は「変化=面倒/不安」として作動しがち。
- 出やすい場面:仕事/消費/人間関係/習慣など様々。
- 付き合い方
① デフォルトを逆手に取る(何もしなくても望ましい行動になる設計)
② 損失と利益を客観視する(書き出してフラットに見る)
③ 小さな実験から始める(安全なテストで参照点をずらす)
現状維持バイアスは”悪癖”やなくて、脳の省エネ機能。戦うより、設計を変えるほうがうまくいく。
次の一回だけ、ハードルをいちばん低くして試す——それで十分。その小さな成功が新しい参照点になって、次はもっと楽に動けるようになる。
「変える」「変えない」を自分で選び直せる状態をつくろう。
参考文献
- Samuelson, W. & Zeckhauser, R. (1988). Status Quo Bias in Decision Making. Journal of Risk and Uncertainty, 1(1), 7–59.
- Kahneman, D. & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47(2), 263–291.
- Tooby, J., & Cosmides, L. (2015). The Evolutionary Psychology Handbook.

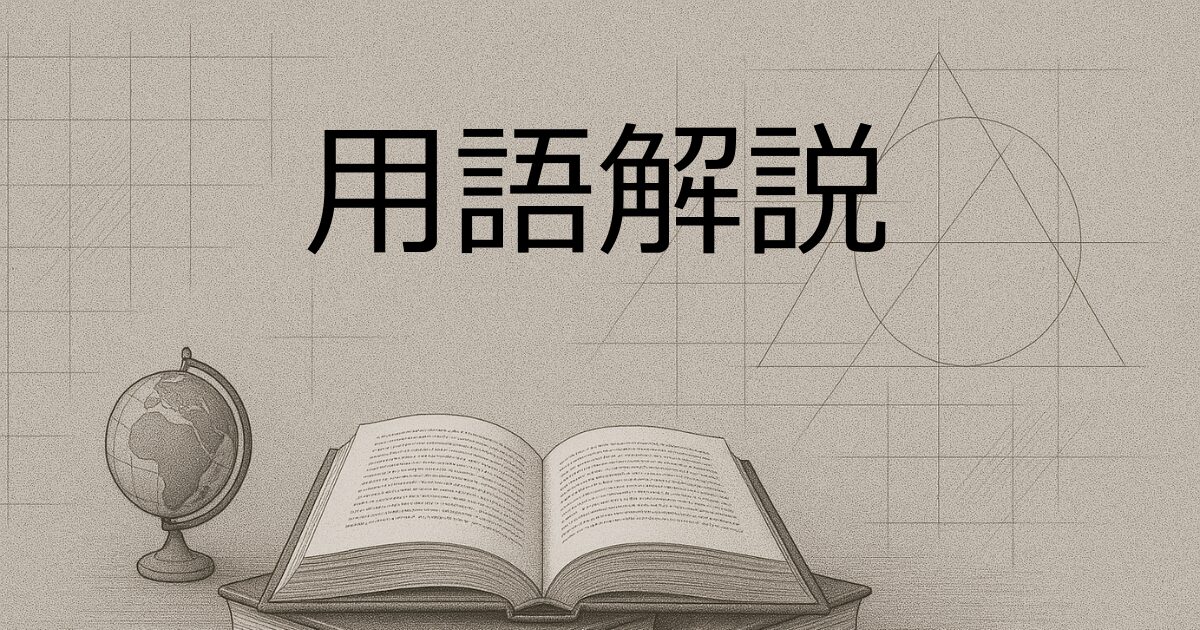
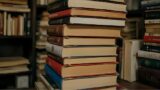
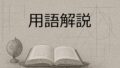

コメント