ナッジ(Nudge)の意味と定義(辞書的解説)
- ナッジ(Nudge)とは、辞書的には「肘でそっとつつくこと」。
- そして行動経済学においては、リチャード・セイラーとキャス・サンスティーンが提唱した概念で、
人々の選択の自由を奪うことなく、望ましい行動をとりやすくする仕組みのこと
を指します。
- 決して「強制」ではない
- そして他の選択の「禁止」でもない
- でも、人はついその方向に動いてしまう
この“そっとした後押し”がナッジの特徴です。
ナッジの基本原則|リバタリアン・パターナリズムとは?
強制でもなく、禁止でもない、ここがナッジの重要なところです。セイラーらは、ナッジを設計する際の基本ルールとして「自由を残す」ことを強調しました。これをリバタリアン・パターナリズムと呼びます。
- リバタリアン=自由を尊重する。個々人の選択肢を狭めない。
- パターナリズム=人々の利益を守る立場をとる。
一見矛盾する2つを両立させるのがナッジの面白いところです。
ナッジをやさしく解説!|二人の本音トーク(事例付き)

要するに人間は”ナマケモノ”やねん。楽な方に流れるから、その流れをデザインするんや

ナマケモノて…まあ否定はできへんけど

階段よりエスカレーター選ぶやろ?でも階段にピアノの音階つけたら、なんか楽しそうでみんな階段使うねん

え、それ面白そうやん!確かに登ってみたくなるもんな!

せやろ?でもナッジは怠けだけやない。あと有名なのは空港の男子トイレの小便器に描かれた”ハエのマーク”や。これ、あったらどう思う?多分”つい狙ってしまう”やろ?

あー、飲み屋のトイレでも的がついてるとこあるな。つまりあれ、酔っ払い相手の”汚され防止ナッジ”かー!

その通り!しかも、実際に”ターゲットシール”として普通に売られてる。店も客もハッピー、これぞ現実に使われているナッジやねん

確かに酔っ払ってふらふらでトイレ使うと、汚してしまうことも多いかもしれへんもんな。シール一枚でトイレがきれいになる可能性が上がるなら、えっらい投資効率やな。

せや。この”ちょっとした工夫”ってのがナッジの特徴や!

なるほどな。でも待てよ、ナッジって良いことにも悪いことにも使えそうやな。

鋭いな!実は確かにそういった例もあってな…まあそれは別の記事で詳しく話すわ
ナッジの有名な事例まとめ|臓器移植・飲食店・空港トイレ
- 臓器移植の同意 日本は臓器提供は初期設定は「しない」。しかし、諸外国の中には初期設定を「提供する」にしている国もある。この場合、提供率は飛躍的に上がる。詳細はナッジ世界編で。
- 飲食店のおすすめ表示 飲み屋の「今日のおすすめ」やランチの「本日の定食」もナッジ。 → 選択肢は自由にあるけれど、人は“おすすめ”と書かれると選びやすくなる。たくさん書かれたメニュー表を見るのが大変、というのは同意できる方多いはず。
- 空港トイレのハエのマーク 上述の通り、男子トイレの小便器に小さなハエの絵を描くだけで、清掃コストが激減した。「思わず狙ってしまう」人間の行動習性を利用したナッジの有名事例。セイラーの著書「ナッジ」もこのエピソードから始まります。
【逆説で学ぶ】ナッジとデザインの関係|自販機のコイン投入口
ナッジを考えるコツは「逆にしたらどうなる?」と考えてみること。たとえば、自動販売機のコイン投入口。
ほとんどの機械は右側についています。もしこれが左側にあったらどうでしょう?右利きが圧倒的に多い社会では、使うたびにちょっとした違和感やストレスが生まれるはずです。つまり「右側」がデフォルトになっているのも、一種のナッジ。
人が自然に動きやすい方向に設計されているんですね。左利きの方には大変申し訳なく思いますが、マジョリティに制度設計を合わせる典型例かもしれません。
駅の改札もそうですね、おそらく左側だと乗客が渋滞する可能性があるでしょう。スムーズな導線のためのナッジの一種とも言えそうです。
こうして“逆説”で考えると、日常のあらゆるデザインにナッジが潜んでいることが見えてきます。
ナッジのメリットと課題|効果と倫理的リスク
- メリット:コストをかけずに人々の行動を変えられる。シール一枚で清掃コストが下がるのは典型例。
- 課題:「操作しているのでは?」という倫理的懸念もある。そもそも「望ましい選択肢」を誰が決めるのでしょう? ナッジを設計するためにはエビデンスに基づいた適切な選択肢を考える姿勢、かつ社会の利益となるような設計を常に考える必要があります。 実際世の中には、「自己の利益を高めるためにユーザーの利便性を無視したナッジ」も横行しています。これは後ほど「ブラック編」で触れていきましょう。
ナッジを設計・運用するためには「透明性」と「自由に選べる選択肢の確保」が必須なわけです。
そして設計者側の「倫理観」も極めて重要です。
まとめ|ナッジは“人間らしさ”を利用した行動デザイン
ナッジは「人間は合理的に行動する」とは捉えず、むしろ「人間はちょっとした工夫で簡単に行動を変える」という事実を原則にしています。
- 私たちは怠ける
- 目先に流される
- つい狙ってしまう・つい手を伸ばしてしまう
- 逆に考えると違和感が浮かぶ
- でもちょっとした仕組みを変えれば、行動も変わる(これは自己ナッジで触れていきます)
そんな“人間らしさ”を味方につけるのがナッジです。
次の記事へ|家庭・自己・世界・ブラック編につながるナッジの広がり
ナッジの基本、なんとなく掴めましたか?
- シール1枚でトイレがキレイになる
- 階段がピアノになれば人は登る
こんな小さな工夫が、実は世界を動かす力を持っています。
ナッジは、自動販売機の投入口といった身近なデザインから、家庭での子育て、自分を律するための工夫、そして臓器移植や選挙制度のように世界を動かす力にまで広がっています。
次回からは、家庭編・自己編・世界編・そして要注意ブラック編へと、実際のシーンごとにナッジの具体例を見ていきましょう。

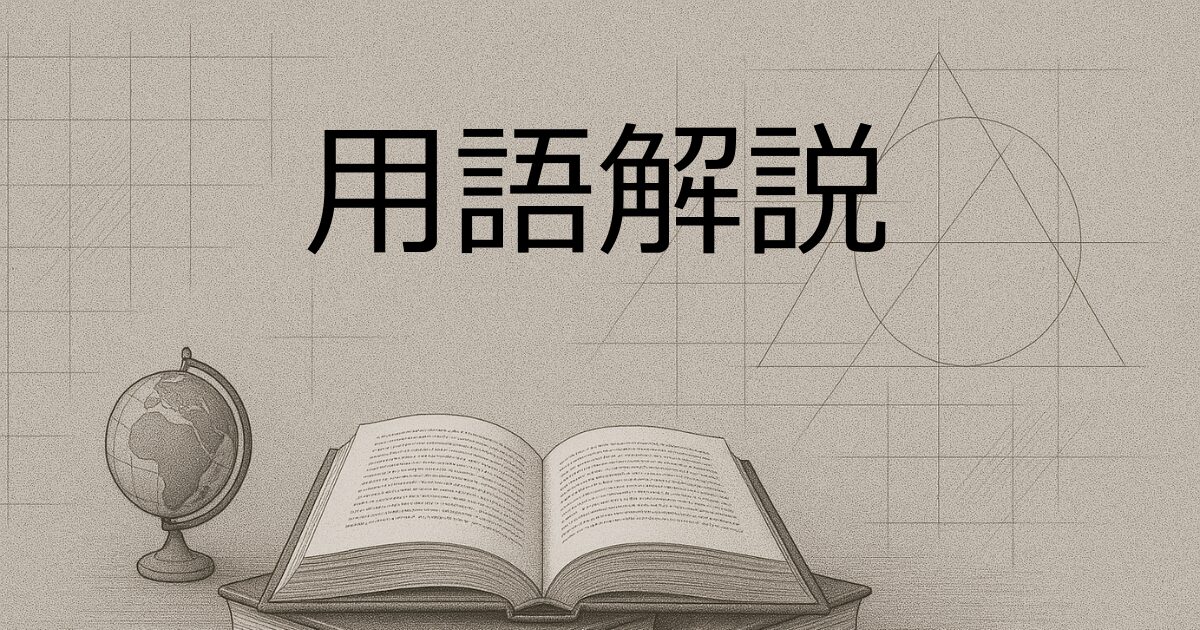
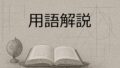
コメント